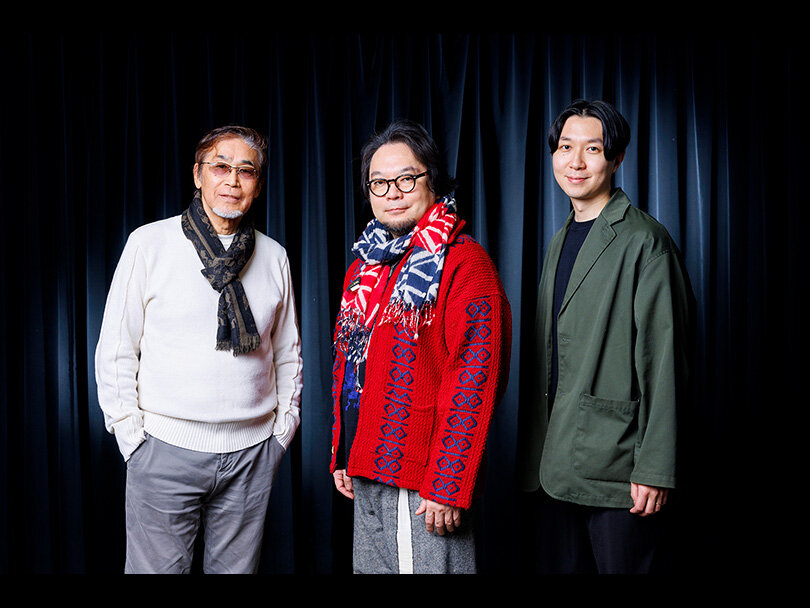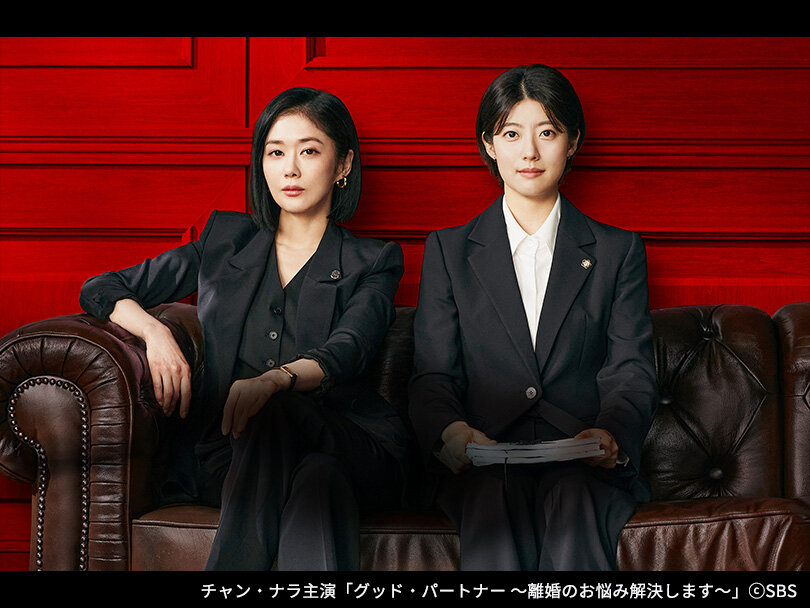「連続ドラマW 石つぶて」で放送ウーマン賞受賞。「負けた戦いに美学があることを描きたかった」
制作局ドラマ制作部プロデューサー 岡野真紀子

「毎日、文化祭があって、その実行委員長をやってるような感じですね(笑)」――。自らの仕事についてそう語るのは、WOWOWのドラマ制作部の岡野真紀子プロデューサー。これまで「なぜ君は絶望と闘えたのか」「しんがり ~山一證券 最後の聖戦~」といったノンフィクション著書原作の、WOWOWならではと言える社会派ドラマを企画・制作してきた。昨年放送された「石つぶて ~外務省機密費を暴いた捜査二課の男たち~」も大きな話題を呼んだが、これらの作品が、30代の女性プロデューサーによるものだとは思いもよらなかったという視聴者も多いのでは? 同作をはじめ、これまでのドラマ制作が評価され、放送界で活躍し優れた功績をあげられた女性に与えられる「放送ウーマン賞」を受賞。30代の女性プロデューサーは、いかにして40~60代の男性が視聴者層の最も大きな割合を占めるドラマを作り上げたのか?
ドキュメンタリーとドラマの交差こそが面白い!
――まず、放送ウーマン賞受賞、おめでとうございます。
ありがとうございます。受賞を知らされた時は、「え? 本当かな?」と(笑)。1973年に始まって、錚々たる方々が受賞されていて、正直、自分が受賞できるということが信じられなくて...。
――今回の受賞を含め、"女性プロデューサー"という部分に焦点があてられることが多いかと思いますが、ご自身は、ドラマの制作における女性プロデューサーという立場について、どのようにお考えですか?
これは私自身の感覚ですが、これまで女性だからという理由で仕事をやりにくいと思ったことは、一度もないですね。TVの視聴者層は、地上波は特にそうですが、女性がとても多いんですよ。そういう意味で、絶対的に男性よりも視聴者に近いところにいる存在だと思います。企画や脚本づくりの流れの中でも、女性であることは、むしろ利点も多いと思います。
――WOWOWのドラマの場合、社会派の作品が多く、地上波とは視聴者の男女比、年齢層が異なるかと思います。
語弊があるかもしれませんが、そういう作品では、むしろギャップがおいしいといいますか...(笑)。世間のみなさんには「こういう作品を作っているプロデューサーは、絶対に(主人公や視聴者層と同世代の)男性だろう」と思われているみたいで。「しんがり」で原作者の清武英利さんに初めて喫茶店でお会いした時も、私を見て「まさかこいつじゃないよな...」と思ったそうですから(笑)。清武さんや、(「なぜ君は絶望と闘えたのか」の原作者の)門田隆将さんといったジャーナリストの方々や、あらゆるスタッフ、キャストとお仕事をご一緒する上で、30代の女性がこういう作品を企画しているというギャップが、いい意味で武器になっているようでして。社会派ドラマを作っているのは、おじさんたちだけじゃないよ! と言いたいですね。
――先ほど、「女性だからという理由で仕事をやりにくいと思ったことはない」とおっしゃっていました。いずれ、どのようなジャンルの作品であれ、女性がプロデューサーであることがごく当たり前になると思いますし、"女性○○"という言葉さえも使われなくなるかと思います。
そうですね。以前、倉本聰さんとお仕事していた時、取材の場である記者が「若い女性プロデューサーとの仕事についてはいかがですか?」ということを聞いたんです。そうしたら、倉本さんは「こいつを若いとも女性とも思ったことはない。一プロデューサーとして他のヤツと何も変わらん」とおっしゃってくださって。その時、初めて「プロデューサーになれたのかな」と思いました。女性だと、気を使われることも多いのですが、やはりプロデューサーとしては"女性プロデューサー"と言われない方がいいんだなとその時、思いましたね。

――WOWOWに中途入社されて、最初に手掛けられたのが、「石つぶて」と同じようにノンフィクション著書を原作に、1999年に起きた光市母子殺害事件を題材にした「なぜ君は絶望と闘えたのか」ですね。なぜノンフィクションのドラマ化ということを考え、この原作に着目されたのでしょう?
私自身、最初は制作会社でドラマを作っていて、AP(アシスタントプロデューサー)をしていたんです。ここでの仕事は、どうしてもスポンサーへの配慮をする部分があり、ドラマを制作する上での制約があったんですね。そんな時、WOWOWの「パンドラ」というドラマを見たんです。
――連続ドラマWの第1弾で、がん特効薬の発見がもたらす、様々な利害関係や国家、組織の闇を描き出し、大きな話題を呼んだ作品ですね。
あの作品は、地上波のドラマでは絶対にできない、あらゆるタブーを破っている内容が詰め込まれていて、すごく面白かったです。こういうのがやりたい! と思って自分でいくつか企画をWOWOWに売り込んだんですが、実績がないこともあってなかなか通らないんですよ。これら企画が通らないはずはない!と思って(笑)。それなら自分でやった方が早いと中途で入社することにしたんです。
――外から企画を持ち込むのではなく、"中の人"になった?
そうです。だから、まず地上波ではできないドラマを作りたいって思いがあったんです。かつ、それまでのお仕事で石橋冠さん(※「なぜ君は絶望と闘えたのか」でも演出を担当)とご一緒する機会があって「本物のドキュメンタリーほどドラマチックであり、ドラマはドキュメンタリー的であるべきだ。その交差が面白い」といった話をよく伺っていたんです。そこで「これだ!」と思えた作品が、門田さんの原作「なぜ君は絶望と闘えたのか 本村洋の3300日」だったんですね。ドキュメンタリーとドラマの交差――それは、その後の「しんがり」も「尾根のかなたに~父と息子の日航機墜落事故~」も同じで、私の中でノンフィクションをやる意味だと思います。
誰も死なない事件で視聴者の心を動かしたのは登場人物たちの感情
――ノンフィクション著書をドラマ化する上で、大事にしている部分、気をつけていることはどんなことですか?
まずひとつは、どういう立場であれ、実在する人物を傷つけないこと。光市の事件で言えば、被害者とその遺族もいれば、加害者もいる。どういう形であれ、双方が嫌な思いをするのは避けたいし、そのためにはあらゆる方法を考えようというのが、私たちのルールです。もうひとつは、ドキュメンタリーを大切にしながらも、あくまでもエンターテインメントであり、ドラマでなくてはいけないということ。事実を伝え、意義を問い続けるだけではなく、しっかりとエンターテインメントであるべきだと思っています。

――いまおっしゃられた中でも、特に後者の点に関して、今回の「石つぶて」では具体的にどういった部分を意識されたのでしょうか?
一番はキャラクターですね。「石つぶて」は、刑事たちが巨悪に立ち向かうも大きな圧力に潰されるという話ですから、後味が良いとは言い切れません(苦笑)。実際に事件を担当された刑事さんたちにお会いしたら、「俺たちは"石つぶて"じゃなく、"石つぶし"。つぶされたんだよ」とおっしゃるんです。
――最後に巨悪を倒して万歳! とはならない...。
ただ、彼らがいまでも抱えているその悔しさを、エンターテインメントとして、主人公の木崎(佐藤浩市)の人間像を、負けはしたけれど、刑事として人間として誇らしく見せるには、どうしたらいいか? そこはかなり作りこみましたし、佐藤浩市さんとも何度も何度も話し合いました。第1話で公園のトイレで木崎が用を足しながら「外務省か...」とつぶやきながら笑ってしまうシーンは、佐藤浩市さんのアイディアです。この主人公が何を思っているのかを視聴者が楽しんで見られるように、人間味を意識して脚本を作っていきました。
――実話をベースにしつつ、結末をフィクションとして変更し、巨悪に打ち勝つという物語にしようとは考えなかったですか?
それは全くなかったですね。どちらかというと、結末よりも事件そのものや刑事の生きざまに惹かれたんですよね。清武さんが「日の当たらない刑事たちが国家の聖域に立ち向かったけど負けたんだ。でも何かが残せたんだよ」とおっしゃって、そのひと言でこの企画をやろうと思ったので、そこを曲げて「勝った! よかった!」とするつもりはなかったです。負けた戦いに美学があるという作品をちゃんとやりたかったんです。
――近年、ある意味でわかりやすい勧善懲悪のドラマが喜ばれる傾向にあります。その中で、結末も含めて、決してわかりやすいとはいえない本作のようなドラマを作るというのは、勇気がいることだと思います。
清武さんが真摯に取材されていて、随時ご報告をいただくのですが、小説ではないので「こうだといいな」「こうなってほしいな」というこちらの望み通りの物語にはならないんですよ(苦笑)。例えば地上波だったら、はっきりとした悪の圧力が描かれるんでしょうけど、実際には明確な圧力がない。悪党たちはみんな笑顔で、その裏でさらりと潰している、でもそのリアルをそのまま描きたかった。この作品は「ウソくさい!」と思われたらアウト。みなさんの税金の話なんですよ! ということを緊迫感をもって感じていただける作品にすることがすごく大事だったので、事実を大きく捻じ曲げるようなことはしたくなかったんですね。
――「石つぶて」に関して、「なぜ君は絶望と闘えたのか」、「尾根のかなたに」、「しんがり」とノンフィクション作品を積み重ねてきたからこその変化、「石つぶて」だからこそできた、これまでの作品にはない部分などはありますか?
ありますね。私もそうなのですが、我々は物語にうねりや派手な展開がないと不安になっちゃうんですよ。そこで音楽を入れちゃったり...(笑)。そもそも不安だから、面白い原作小説にすがりたいという気持ちもあります。でも、ノンフィクションを元にしたドラマを作っていく流れの中で、物語のうねりや変化、起承転結よりも、そこで起きている精神的な部分、キャラクターの感情そのものだけで、ドラマになるんじゃないかと感じれたんですね。それはこれまでの作品でも感じてたんですが「石つぶて」はその集大成といえる作品だと思います。
――と言いますと?
全8話ですけど、事件はたったひとつで誰も死なない。でも、それでドラマを作れるという自信になりました。起きた事象ではなく、小さくても一つ一つの事象に対し登場人物たちが何を感じたかで、視聴者の心を動かすということが、今回はできたんじゃないかと思います。スタッフ、キャストも最初、1話ずつ異なる金融事件を扱うのかと思っていたそうで、8話でひとつの事件と聞いて「大丈夫なの?」と言われたのですが、やってみると「結構、大丈夫だね」と。毎回、何かが起きて、誰かが死んで...ではなくても見せられるんだって自信になりました。

――地上波では視聴率が常にニュースとしても報道され、大きな影響を及ぼしています。WOWOWは有料放送ということで、そうした流れとは異なるかとは思いますが、プロデューサーとして視聴率や、視聴者の評価といった部分はどのように考えていらっしゃいますか?
地上波の方々も視聴率にかなり左右される部分があるかと思いますが、私たちも同等か、それ以上に左右されますね。もちろん、その数字によって、ものづくりを変えようとは思いませんが、WOWOWの場合、月々お支払いいただいているお金で、面白くないものを作ったらアウトだと思っています。だから、加入者の方がどれくらい見てくださっているのかはすごくシビアに見ていますし、それが低かったら悩むのは私たちも同じです。加えて、新しい方に加入していただくというビジネスモデルですから、そこに対する焦りもあります。ビジネスという点では、常に1作1作が勝負ですね。
――視聴者層という点では、地上波とは大きく異なるかと思います。
そうですね。地上波の場合、どうしても視聴層が広すぎて、見えづらい部分もあるでしょうし「なるべく多くの人々に見てもらおう」という部分もあると思います。私たちの場合は、どこかで「このドラマはここ!」とターゲットを決めて、誰にでもわかるドラマとしてではなく、コアな層に見ていただければと考えているところはあると思います。
――「石つぶて」に関して、放送後の反響はいかがでしたか?
電話やネットを通して多くの声をいただきましたが、すごくよかったと思います。もっと「難しくて分かりづらい」と言われるかと思っていたんですが、見てくださった方のテンションが上がっているのを感じました。WOWOWにしかできないテーマに、視聴者のみなさんがちゃんと乗ってくださったのが嬉しかったですね。それから、今回ほど他局の方から声をかけていただいた作品はなかったですね。
――同じ業界内でも話題になっていたということですね。
いままでもお声をいただくことはありましたが、その中でも一番多かったです。今回、私がこうして「放送ウーマン賞」をいただけたのは、業界の中でこの作品を知って頂けたからなのではと思います。

「悪い男を魅力的に描く」女性プロデューサーならではの視点
――ここから改めて、女性プロデューサーという点についてお伺いしたいのですが、本作において、女性プロデューサーの視点が活かされている部分はどういうところだと思いますか?
一番大きいのは、外務省の機密費詐取の犯人である真瀬(北村一輝)という男性のキャラクターですね。彼の女性とのシーンの描き方――なぜか女たちが彼について行ってしまう、そんな魅力的な男性に描きたかったんです。男性陣はどちらかというと「真瀬に石を投げろ! 俺たちの税金を奪ったヤツだ!」というテンションが強くて、そこは作品を作っていく上で、大きな違いだったと思います。
――悪い男ではあるんだけど、女性から見て魅力的に見える犯人像?
魅力的だからこそ、太刀打ちできない刑事がいるということを大事にしたかったんですね。そこは、私が女性だから、彼の色気にやられたんだと思います(笑)。あぁ、たしかにこういう男だと、女はついて行っちゃうよね...と。たくさんの愛人がいたということで、どんな魅力があるんだろう? とそこはすごく調べましたね。単に私の興味なんですけど(笑)。組織論とかよりも、個々のキャラクターに興味を持つのは、私が女性だからというのは大きいのかもしれません。あとは、主人公の家庭をほとんど描いてないんですよね。
――従来の刑事ドラマであれば、主人公が家庭で癒されたり、逆に娘との関係で問題を抱えていたり...という"家庭の事情"が多少は描かれることが多いですね。
これは、まず佐藤浩市さんから「私生活を全く描かなくて良いのでは」とご提案を頂いたんです。私もまさに同感!でした。あまり興味ないんですよ(笑)。家に帰って奥さんが作った料理を食べたり、愚痴ったりとか。男性はそこに癒しを求めてるのかもしれませんが...。そこは徹底して描かないことにしたんです。

――ご自身が"クリエイター"であるという意識はお持ちですか?
自分がクリエイターだと思ったことは一度もないですね。気分的には毎日が文化祭で、その実行委員長をやってる感覚です(笑)。めんどうくさい委員長だと思いますけど「ちょっと! 今日のお弁当おかず少ないんじゃない? お弁当はみんなのモチベーションなんだから!」って怒ってる感じ。クリエイターというよりも、そうやってみんなのテンションを上げ、一緒に面白いものを作っていくという感覚です。そういう意味で、自分にはクリエイティブな仲間がいるんだと思います。「面白いことやりたい!」と言った時、「やろうぜ」と集まってくれる仲間がいる。ドラマを作ることを"仕事"と意識したこともないんですよ。自分が「やりたい」と思ったことを仲間を呼んで「やっちゃおう!」ってやってる。やっぱり、実行委員長ですね。365日、24時間、実行委員長です(笑)。
30代半ばを過ぎた今だからこそ、あえて挑戦したい「同世代に向けた等身大のドラマ」
――今後、どのような作品を作りたいですか? ノンフィクションではなく、フィクション作品を作ってみたい気持ちなどはありますか?
ありますね。もちろん、引き続きノンフィクションもやっていきたいですが、私の中で、プロデューサーがネタ探しに本屋に通うようにはなりたくないというのがあるんですよ。もちろん「この本はすごく面白かったのでドラマにしたい」という場合はあるでしょうけど、企画を出さなきゃいけないからと本を読むようにはなりたくない。そんな思いもあって、いま、やろうと思っているのは自分と同じ世代を題材にした等身大の作品です。
――「しんがり」「石つぶて」と登場人物も視聴者のターゲット層も40代、50代、60代の作品が大きな反響を呼んできましたが、あえて同世代の等身大の作品を?
いままで40代、50代という上の世代に向けて、背伸びしていた部分があったと思うんです。いま自分が30代の半ばを過ぎて40代が近づいてきた時、初めて等身大と言えるドラマを考えていて、背伸びせずに自分自身の感覚、選択でドラマを作ってみたいなぁと。
――同世代を描くのと、少し背伸びして上の世代を描くのでは、どちらが難しいと思いますか?
違う世代を客観的に見て、勉強しながら作品を作ってきました。知らないからとことん勉強する。同世代が「わかってる」と思いながら作るものって、実はわかってないものが多いのかもしれません(笑)。そういう意味で、50代の人が50代のドラマを作るよりも、私の方が客観的に研究して作っているという感覚はあったし、そこで背伸びをして作っている方が心地よくはあるんですが...。
――そこであえて、挑戦したい?
同世代の人間に「違う」と思われない、同世代の等身大のドラマをちゃんと作ってみたいという気持ちですね。