プロモーション映像『WOWOWにおいで。』ができるまで――プロデューサーと監督の幸せな関係
映画監督 早川千絵/編成局編成実施部ユニットリーダー 谷田篤

のどかな田舎を舞台に、まるでドキュメンタリー映画のような、美しく、みずみずしい映像が印象的なWOWOWのプロモーション動画『WOWOWにおいで。』(夏休み篇)が先日より放送されている。監督を務めたのは早川千絵。短編『ナイアガラ』が2014年カンヌ映画祭に入選し、日本を代表する名匠・是枝裕和監督が総監修を務めるオムニバス映画『十年 Ten Years Japan』のうちの一編を任されるなど、注目を集めている新鋭監督だ。そんな彼女は、昨年春まで約10年にわたってWOWOWで働いていた。今回の『WOWOWにおいで。』を早川監督に依頼することを決めた編成局 編成実施部の谷田篤は、映画部時代、早川監督の同僚でもあった。どのような紆余曲折を経て、2人が監督とプロデューサーという立場で再会し、この美しい映像が生まれるに至ったのか――?
「恥ずかしくて言えなかった」WOWOWで働きつつ、内緒で通った夜間映画学校
――早川監督はアメリカの大学で勉強され、その後、現地での仕事を経て、2008年に日本に帰国。業務委託という形でWOWOWで働きはじめたそうですね。
早川 大学を卒業して1年ほどニューヨークの日系のテレビ局でアシスタント業務をしていました。日本時間の早朝にニューヨークから生放送される経済番組があって、そのアシスタントをしたり、ちょうど「9.11」が起きた時期だったので、日本からの取材も多く、コーディネートや通訳などをしていました。
その後、映画を作りたいと思い、全ての仕事を辞めたのですが、そのタイミングで妊娠していることがわかり、そのまま2人の子どもを出産しました。2008年に帰国し、WOWOWに勤めていた友人から英語ができる人材を探していると聞き、業務委託として勤めることになりました。
――入社後のお仕事は?
早川 放送される映画をはじめから終わりまで見る全編プレビューという品質確認の業務から始まり、その後、アメリカのメジャースタジオから素材を取り寄せ、日本のポストプロダクション(映像作品の編集・加工を手掛ける制作会社)にWOWOWが放送するフォーマットに仕上げていただく放送素材の制作管理などをずっとやらせていただいていました。

――WOWOWで働きつつ、映画学校の夜間監督コースに通い、卒業制作として『ナイアガラ』 を監督されたんですね?
早川 そうです。2012年から通い始めました。映画を作りたいと思いつつ、アメリカでは子育てがあり、日本では仕事が忙しく、取りかかれていなかったのですが、このまま年齢を重ねると撮れなくなってしまうと思い、1年間だけ通える夜間の学校に通い始めました。でも、WOWOWはプロフェッショナルなプロデューサーたちがいる会社なので、ずっと(映画学校に通っていることを)恥ずかしくて言えなくて...(笑)。
――そもそも、アメリカの大学で学ばれたのは映画ではなく写真だったそうですが、映画を志すようになったのは?
早川 実は中学の頃から映画監督になりたいと思い、大学も映画学科に入ったのですが、入学当初はまだ英語もろくにできず、周りの同級生はゴツい男の子ばかりで「ここじゃやっていけない!」と怖じ気づいてしまい、逃げるように写真学科に移ったんです(苦笑)。でもそれがすごく楽しくて、写真を学びつつ、自分でビデオカメラを買って、独学で撮影や編集を学びながら「映画を撮りたい」って思っていました。
――谷田さんは、2002年にWOWOWに入社し、2016年に編成に異動され、番宣制作担当になられています。現在の具体的な仕事内容について教えてください。
谷田 編成に異動してから約2年間はスポーツ番組の編成を担当していまして、今のOAP(オンエアプロモーション)の担当になったのは昨年の7月です。いわゆる"番宣"といわれる、番組と番組の間に流れる15秒や30秒などの短い番組宣伝の映像を作っています。
WOWOWでは放送の3か月前に編成会議があって、そこで3か月後の番組が全て決まります。それを元に、OAPで「この番組は30秒と60秒の番宣を作ろう」「いつからいつまで流そうといった全体のプランを立てます。OAPチームには6人ほどのプロデューサーがいまして、それぞれの担当ジャンルの素材を集め、制作会社さんと制作の方向性を決め、出来上がったものを番組担当のプロデューサーに確認してもらってから、放送するという流れで、月に何百本という数を作っています。
――現在の部署に配属される以前はどのような部門でどんなお仕事を?
谷田 最初は顧客サービス部、次に営業企画部で、それぞれ2年半ほど。その後、広報部に5年ほどいて、それから映画部に4年半いました。
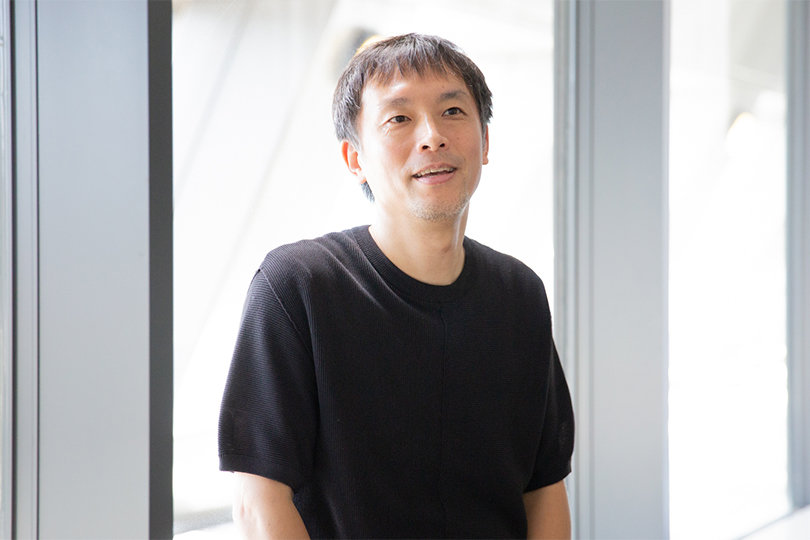
――その映画部でおふたりは同僚だったわけですね?
谷田 そうです。僕が配属されたのが2012年で、その時にはもう千絵さんはいましたね。配属されて最初の2年半ほどは海外メジャースタジオの担当として、各スタジオの作品の購入や海外ドラマの日本語版の制作などをしていて、一緒にお仕事をする機会も多かったです。
――当時のお互いの印象は? まさかそれから数年後に、監督とプロデューサーという立場で一緒に仕事をし、こうして一緒に取材を受けることになるとは思っていなかったでしょうが...。
早川 (今回の仕事の依頼が)一番意外なところから来ましたね(笑)。ビックリしました。面白いなぁと。谷田さんは正直で、すごく正義感の強い人だなという印象がずっとありました。
谷田 合ってます(笑)。千絵さんは...。
早川 怖かった(笑)?
谷田 たしかに怖かったかな(笑)。
早川 「あの素材まだですか?」「映画のタイトルリスト、まだ来ないんですか?」とか、いつも突っついていたので。
谷田 でもね、声は張らないんですよ。声を張らない怖さがありました(笑)。あとは、いつも人間観察をしていましたね。
早川 私がですか? してないですよ!(笑)
谷田 いや、してたしてた(笑)。
――当時、谷田さんは早川監督が映画学校に通われていることや映画監督を志していることを知らなかったんですよね?
谷田 全然知りませんでした。(知ったのは)いつかな?『ナイアガラ』でカンヌに行ったとき?
早川 『ナイアガラ』がカンヌ国際映画祭シネフォンダシオン部門に入選して、カンヌに行くことになったときに、ちょうどWOWOW FILMSの『2つ目の窓』(河瀬直美監督)もカンヌに出品されていて「すみません、実は私も行くことになりまして...」と部の人たちに報告しました。
谷田 休みを取ってカンヌに行かないといけないですからね。
早川 カミングアウトでした(笑)。

仕事中に突然届いたカンヌ国際映画祭入選のメール
――『ナイアガラ』のカンヌ国際映画祭での入選までの経緯について教えてください。
 『ナイアガラ』
『ナイアガラ』
早川 卒業制作の作品ができて、片っ端から締め切りが近い映画祭に送っていました。カンヌは締め切りが2月で「あ、カンヌも受け付けているのね」くらいの気持ちで、まさか入選するとは思ってなくて。いつ発表されるかも知らないまま送ったのですが、突然、メールが届きまして...。それこそ仕事中にメールが来て、手が震えました。誰かに言いたいけど言えない! って(笑)。
谷田 行動力が本当にすごいですよね。普段、内に秘めた"情熱"みたいなものがなかなか外には伝わってこないんですけど(笑)。
―― 入選の連絡はどのように?"入選の"知らせでしたか?それとも映画祭への招待でしたか?
早川 最初のメールは(入選作を)選んでいる映画祭のプログラマー本人からで、「これは学校で制作したものですか?」「DCP(デジタルシネマパッケージ)を作ることはできますか?」といった質問で。その時点で選ばれたかどうかは書いてなくて、ぬか喜びはできないなと思っていましたが、翌日「おめでとうございます」と正式に入選の知らせが届きました。
――実際にカンヌに行かれて、現地での反応などはいかがでしたか?
早川 本当に夢のような時間でした。学生向けの部門ではありますが、世界中の名門校の生徒がかなり製作費もかけて作っている作品が多い中で、自分でカメラを回した素人くさい私の作品が混じっていて(笑)、「こんなんで大丈夫なの?」と思ったのですが、現地でも受け入れていただいて「あなた、映画の世界に来ていいよ」と言われた気がして嬉しかったです。
現地では「優しい映画だ」という声をよく聞きました。登場人物たちへのまなざしが優しいという意味だと思うのですが、自分ではそういう映画を撮ったつもりがなかったので意外でもありました。でもその後、映画を作り続けて行く中で、その言葉が腑に落ちてきた部分はありますね。
――その後、国内の若手映画監督の登竜門といわれるぴあフィルムフェスティバル(PFF)でもグランプリを受賞されています。
早川 PFFは憧れの映画祭で、まずは1次審査通過できれば...と思い、送っていたので、入選の知らせが来た時は嬉しかったですね。授賞式では順番に賞が発表されていくのですが、短編作品でグランプリはありえないと思っていたので、(グランプリのひとつ前の)準グランプリが発表された時点で「ダメだった! 会社のひとに何て言おう...」って(笑)。その時はもう会社の人も全て知っていて、皆に送り出され、早退して授賞式に来ていたので...。だからグランプリをいただけてホッとしました(笑)。
谷田 簡単に言いますよね(笑)。

――その後、是枝裕和監督の監修による『十年 Ten Years Japan』に参加されることになりますが、この作品が動き出したのは...?
早川 2017年の6月ですね。カンヌで知り合った日本人のプロデューサーの方から数年ぶりにメールをいただいて「いま、こういう企画があって、コンペ形式だけど企画を出しませんか?」と。

 『十年 Ten Years Japan「PLAN75」』2019年11月放送
『十年 Ten Years Japan「PLAN75」』2019年11月放送
――早川監督が担当された「PLAN75」は高齢化問題を解決するために、75歳以上の高齢者に安楽死を奨励する国の制度「PLAN75」の勧誘を仕事とする男性を人公にした作品です。どのようにして物語を構想されたんでしょうか?
早川 2017年の初めに長編映画として構想していた企画だったんですが、『十年 Ten Years Japan』が社会的なテーマで10年後の日本を描くということでぴったりだなと思って短編用に書き直しました。
一番大きかったのは、その前年に相模原の障がい者施設で起きた殺傷事件ですね。ものすごく大きな衝撃を受けましたし、社会の受け止め方――世の中の空気が殺伐としていっているのを感じて、思い浮かんだストーリーでした。
――是枝監督と具体的に作品について話したりすることはありましたか?
早川 何度かお会いしたり、またメールを通してもアドバイスをいただく機会はありました。思っていた通りの方といいますか、あんなに有名で実績のある監督なのに、私たち若手の監督たちに対しても「監督は君たちだから」と常に作家として尊重してくださるし、「こうじゃなきゃいけない」とか「これは間違っている」という言い方を絶対にされない方でした。
退社して改めて感じる、面白いことに貪欲なWOWOWの風土、作品の面白さ!
――そして2018年にWOWOWを退社されました。約10年にわたって働いて、その後もWOWOWとお仕事をされていますが、早川監督から見て、WOWOWはどういう会社ですか?
早川 今回、お話をいただけたこともそうなんですけど、柔軟で面白いことに対して貪欲な会社ですよね。「いいものを作りたい」というのを第一に掲げていて、どの部署でどういう番組を作り、どういう作品を選ぶにせよ、「ここに任せておけば間違いない」ということを感じさせてくれますね。
それは働いているときも思っていましたが、退社してからさらに強く感じます。「以前、WOWOWで働いていました」と誇りを持って言えますね。そうすると、みなさん「WOWOWってあの番組が面白いよね」「あのドラマいいね」とおっしゃってくださるんです。
中にいると、WOWOW社員のみなさんは自分たちのことを褒めないので、厳しい意見ばかり耳にしていましたが、外に出てみて、すごく高い評価を受けているんだなと改めて感じました。
――WOWOWで働いた経験が、ご自身のクリエイティブな部分に活きていると思いますか?
早川 めちゃくちゃ活きていると思いますね。広告やCMの仕事もするようになって、企業さんを相手に仕事をする中で、WOWOWで働いていた経験があるからこそ、企業側の気持ち、どういうメッセージを伝えたいかを感じやすいと思います。
加えて、「ものを作る」「ゼロからコンテンツをさがす」会社にいた中で、自然と学ばせていただいたことも多かったと思います。何を求められているのか? 単に自分が作りたいものを作るのではなく、観る人の存在を考えて、彼らがどういう作品が見たいのか? ということを考えるようになりました。
普段の"プッシュ型"番組宣伝とは異なるイメージ番宣の面白さ、難しさ
「WOWOWにおいで。」夏休み篇
――続いて、今回の『WOWOWにおいで。』についてお伺いしていきます。谷田さんは現在の仕事で各番組の宣伝映像を作っているとのことでしたが、それとは異なるWOWOW全体のプロモーション映像であるこの『WOWOWにおいで。』を制作されることになった経緯は?
谷田 6月の上旬ごろ、編成のデスクから「家族、子どもたちの在宅率が高いお盆、夏休みに向けて、WOWOWを見てもらえるようなイメージの番宣を作ってもらえないか?」という話がありました。
時間はないけど頑張ってやってみようと動き出したのですが、イメージ番宣って意外と難しくて。番宣なので、番組の情報が載っていないといけないけれど、その上で"家族でテレビを見たくなるような映像"とフワッと言われても...(苦笑)。
そうこうしている間に、僕にこの仕事をオーダーした編成のデスクをはじめ、一緒に作ろうとしていたメンバー全員が人事異動で部を離れることになってしまいまして...。もうできることをやっていくしかないな、と思っていたときに千絵さんと偶然、ばったりと会ったんです(笑)。
早川 共通の知り合いのいる飲み会で。「お久しぶりです」って(笑)。
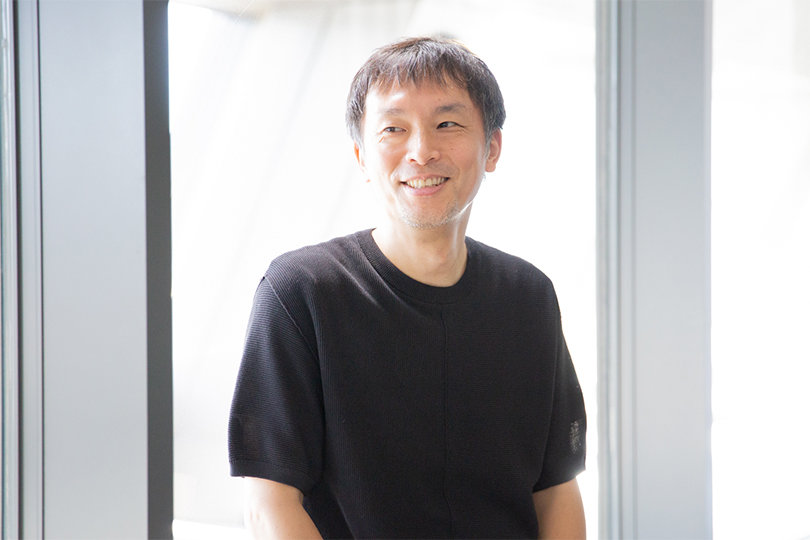
谷田 ただ、前々から千絵さんの映画を見ていまして、『十年 Ten Years Japan』の中でも千絵さんの「PLAN75」はダントツだなと思っていました。あの作品に限らず、早川監督の作る作品の世界観がすごく好きでした。日常の中の静かな一部分が切り取られていて、映画の最初と最後で何が変わったわけでもないのに、何かを与えてもらっているような。
いわゆる番宣というのは"プッシュ型"と呼ばれる、文字通り、バンバンバンッと情報を押していくものが多いんですが、今回は、その中でフッと心が休まるようなものが作れたら...という話をデスクとしていたんです。
あと、偶然ですが僕も早川監督も子どもが2人いて、一緒に働いていた当時から子育てについて話をする中で、家族や子どもについての考えを共有しているような思いもあり、今回のコンセプトと照らし合わせても適任なんじゃないかと思えたんです。
早川 (飲み会で再会後にオファーの)電話をいただきまして、嬉しくて、すぐに「やりたい!」と思いましたし、話している間にいろいろアイディアがわいてきて「夏休みの...」と言われたのに、夏と秋と冬の話まで浮かんできました(笑)。「あぁ、わかるわかる! こういう感じですよね?」って。
6月19日に電話をもらって「7月末から番宣を流したい」と言われ、私も7月はちょうど忙しくてスケジュールが心配だったのですが、こういう縁で始まる企画はたいていはうまく行くって思いもあったんで「大丈夫ですよ」と(笑)。
――夏休み中の孫2人を田舎で祖母たちが迎えるというストーリーラインはどのように?
谷田 先ほども言いましたが、最終的にテレビ、WOWOWに結び付けないといけないんですが、最初に「たとえば...」という感じで話をしたときに、いくつか出したアイディアのひとつとして「おじいちゃんの家がWOWOWに加入していて、そこに行く」というものがありましたね。ただ、そこまで長々と説明をしたわけでもなく...
早川 「夏休みにおじいちゃんの家に子どもたちだけで遊びに行く」みたいな? くらいの感じで。
――企画から撮影、完成までかなりタイトなスケジュールだったようですね。
谷田 (企画をしたのが)梅雨真っ最中で、夏の画はその時期は撮れない。そうなるとやはり梅雨明けの7月後半にならないと撮影はできない、でも7月の後半から放送したいから、撮ってすぐに放送するしかないなと(笑)。
千絵さんも7月前半は忙しかったので、逆にその時間をロケハンや構想、オーディションに使おうということになりました。子どもたちを起用するので、土日の撮影が基本で、7月の20日、21日、もしくは27日、28日くらいしかチャンスがなく、それなら20日、21日に撮影して、7月中に仕上げようと。
プロの子役ではない、本物の姉弟を起用した独特の撮影現場
――撮影はいかがでしたか?
早川 最初の電車のシーンは茨城県のひたちなか市で、おじいちゃんの家のシーンは千葉県の木更津でしたが、現場ではもう夢中でした。
自然な様子の画が取りたかったので、子どもたちには詳しいことを何も知らせておらず、彼らからしてみたら「朝早くに知らない場所に連れてこられて、この大人たちは何してるの?」という感じだったと思います。いきなりそこで「遊んで」と言われても戸惑いますよね。本当はもっとゆっくり時間をとって、引き出していかないといけなかったんですが...(苦笑)。でも1日で撮影を終えなければならない状況で、スケジュールもギリギリだったので、その中でなんとか撮らなきゃいけないと必死でした。ただ、だんだん撮影が進む中で、子どもたちも慣れていき、本当に素晴らしくて、助けられましたね。


――あの子どもたちは実際の姉弟なんですか?
早川 そうです。本当の姉弟です。
谷田 あの2人に決定するまでにもいろんなことが...(笑)。
早川 私の中ではあの2人と決めていたんです。1年ほど前に彼らに出会って、「この子たちいいなぁ」という思いが残ってて、今回の企画が動き出した時点で「絶対にあの子たちで撮りたい」と思っていました。
谷田 プロの子役ではないので、演技指導などをしても意味がないので、そのままのあの子たちを撮ったし、それが早川監督のやりたいことでもあったので、そういう意味でも独特の現場でしたね。
早川 カチンコを使うのもやめましたし。
谷田 決められたとおりにみんなが動くんじゃなく、自然のままに子どもたちが自分たちの興味のままに動く姿をとらえていくという感じで、子どもたちが勝手にカエルを見つけてくれたり(笑)。やはり、そうした方がいいものが撮れるんですよね。

「言葉で表現できないことを映像で表現したい」
――早川監督は普段からどのようにして作品のアイディアやインスピレーションを得ているのでしょうか? 影響を受けた映画作品などはありますか?
早川 映画に関して言うと、ドキュメンタリーや新聞の三面記事を見て思いつくことが多いですね。それから、影響を受けた映画としていつも言っているのは、小学生の時に見た小栗康平監督の『泥の河』ですね。そこで作り手側を初めて意識したというか、これまで自分が言語化できなかった感情が表現されていて、映画ってすごいなと思ったのと、自分の気持ちをわかってくれている人がちゃんといるんだということが初めてわかった体験でした。
――現在、映画やCMなど様々な作品を撮られていますが、作品を作る上で大切にされていることはなんですか?
早川 映画とCMでは異なるんですが、CMに関して言えば、依頼をくださった方に喜んでほしいというのが一番大きいですね。何を求められているのか? というのを考えるのはすごく大事なことで、自分の得意な分野で人を喜ばせることができるというのが幸せですね。
映画に関して言うと、言葉で表現できないことを映像で表現したいという思いがあります。日本に限らず、どこでいつの時代に見ても心に残るようなものを作りたいなと思っています。
――谷田さんは現在の番組宣伝のお仕事をする上で大事にしていることは何ですか?
谷田 やはり基本的なことが一番大事で、放送日時なども含めてしっかりと情報を伝えるというところですね。各番組にはプロデューサーがいるので、そのプロデューサーの期待に応える番宣にしたいなと思っています。その上で、自分たちのクリエイティビティをどこまで発揮し、15秒、30秒に込められるか? ということを考えています。
――今回の『WOWOWにおいで。』のような映像は、普段の番宣以上にクリエイティビティが求められるところが大きかったかと思います。
谷田 普段は素材も限られて制限もある中で作っていますが、今回、そういうものから解き放たれたというのはありましたね。千絵さんと一緒に仕事をさせてもらって、そのすごさを改めて感じさせられた部分も大きかったですね。
先ほどの子どもたちの話だけでなく「音楽はこれがいい」「ナレーションはこの人じゃなきゃダメ」(ナレーションは早川監督の強い要望で玉井夕海さん〈歌手、女優〉に依頼)と、自分のやりたいことを全部実現していくんですけど、そこまで強くイメージを持っていて、主張を押し通し、結果的にそれによって、作品を僕がプロデューサーとして求めている以上のものにしてくれるんですね。それはすごく幸せなことでした。
プロデューサーが「こうじゃなきゃダメだ」とあれこれ口出しして作品をつまらなくしてしまうのは一番やってはいけないことなんですよね。監督の中に確固としたイメージがあって、それを「いいな」と思えて、僕はお金の調達や社内の調整、環境づくりに集中できる。それが幸せなことで、いかに大切かというのを今回、強く感じることができました。

取材・文/黒豆直樹 撮影/祭貴義道 制作/iD inc.




