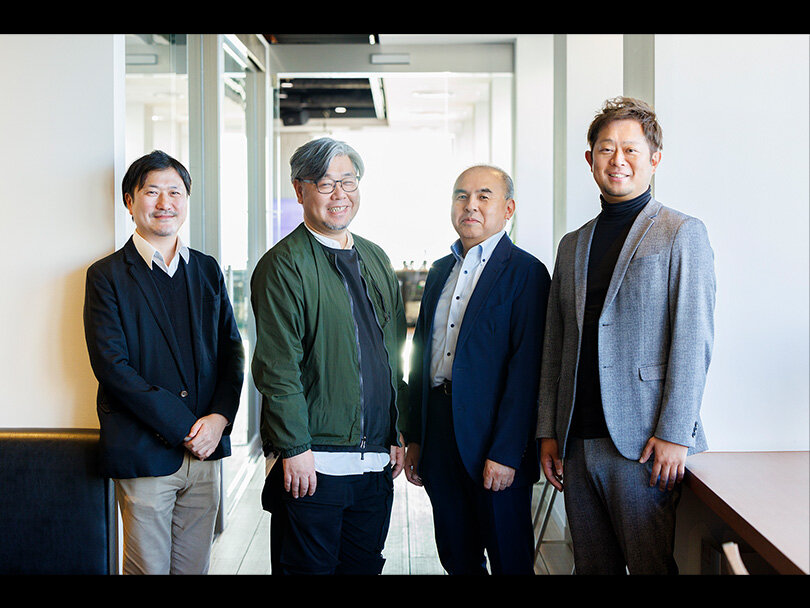富士山麓で開催されたキャンプフェス『FUJI & SUN '22』レポート。「本物の体験」をコンセプトに地元と作り上げる、WOWOWらしいフェスのあり方とは?

5月14、15日の2日間にわたり静岡県富士市・富士山こどもの国にて開催されたWOWOWが主催するキャンプフェス『FUJI & SUN '22』。2019年に初回が開催されて以来、今年で3回目となった同フェスだが、2019年の第1回にはエルメート・パスコアールやセオ・パリッシュといった海外の大物が出演。第1回、第2回には、林立夫、矢野顕子、大貫妙子のような国内のレジェンドアーティストも連続して出演するなど、富士山を望む最高のロケーションとともに、世代もジャンルも越境したミュージシャンの出演が『FUJI & SUN』の一つの大きな特色になっている。そんなさまざまな出会いを演出するのは、国内外のさまざまなカルチャーを紹介してきたWOWOW主催ならではといえるだろう。音楽とキャンプがシームレスにつながる開放感あふれる空間、そして出演するアーティストもロックにジャズにヒップホップに環境音楽、ベテランから若手までを網羅する、そんな多文化的なキュレーションは今年も健在である。
1日目は、前日の朝まで大雨が降るという不安要素はあったが、当日は小雨が時折降る程度。深夜の雨と風の影響でステージのセッティングに時間がかかったことで開演時間に遅れが出たり、予定されていたオープニングセレモニーが中止になるなどのハプニングはあったものの、無事開催に至った。
今年の『FUJI & SUN』には三つのステージがあり、大きい順に「SUN STAGE」、「MOON STAGE」、「STONE STAGE」となる。いわばフェスの顔となるアーティストたちが出演し、飲食や物販、アクティビティも充実している「SUN STAGE」。アコースティックな魅力を放つアーティストたちの演奏や、有名アーティストの実験的なパフォーマンス、さらに地元に根差した活動をしている音楽家が出演したり、トークセッションがあったりと、フェスならではの広がりと奥行きを体現する「MOON STAGE」。そしてDJをメインにした、コアな音楽が流れ続ける「STONE STAGE」。それぞれが独立した特色を持ったステージだ。

各ステージ間の移動には5~10分程度を要するが、SUN STAGEからMOON STAGEに移動する道すがらでは、会場となる富士山こどもの国で飼育されているアルパカや馬、ヤギなどの動物たちを見たり触れたりすることができたり、アスレチックがあったりと、そうしたロケーションも含めて、人と自然がつながり合う空間全体を楽しむことに醍醐味があるフェスといえるだろう。
 また、地元の有名店やクラフトビールも堪能できるフード、キャンプ関連のショップや体験講座などさまざまなアクティビティも会場内では展開されており、見渡してみれば、場内には小さなお子さんを連れた家族で来ている人たちがたくさん見受けられる。ステージ上のアーティストを見つめるだけではない、多様な楽しみ方があるキャンプフェスならではの光景が広がっていた。
また、地元の有名店やクラフトビールも堪能できるフード、キャンプ関連のショップや体験講座などさまざまなアクティビティも会場内では展開されており、見渡してみれば、場内には小さなお子さんを連れた家族で来ている人たちがたくさん見受けられる。ステージ上のアーティストを見つめるだけではない、多様な楽しみ方があるキャンプフェスならではの光景が広がっていた。
出演アーティストたちを、写真とともに振り返ろう。まずは1日目。 予定されていたステージ間の行脚は雨の影響で残念ながら中止になったものの、その獰猛なパフォーマンスでみごとにフェスの開幕を宣誓した切腹ピストルズ。
予定されていたステージ間の行脚は雨の影響で残念ながら中止になったものの、その獰猛なパフォーマンスでみごとにフェスの開幕を宣誓した切腹ピストルズ。 キュートな衣装と幅広い音楽性とともに「自由」を体現してみせたCHAI。その高い演奏力はいわずもがな、さらにダンスやエレクトロニクスを取り入れたステージングは華やかでクールだ。
キュートな衣装と幅広い音楽性とともに「自由」を体現してみせたCHAI。その高い演奏力はいわずもがな、さらにダンスやエレクトロニクスを取り入れたステージングは華やかでクールだ。 フェスの地元・富士市吉原を拠点に活動する吉原祇園太鼓セッションズの開放感あふれる演奏と、その後のトークセッションでまさかの飛び入り参加した富士市市長・小長井義正氏の太鼓実演!
フェスの地元・富士市吉原を拠点に活動する吉原祇園太鼓セッションズの開放感あふれる演奏と、その後のトークセッションでまさかの飛び入り参加した富士市市長・小長井義正氏の太鼓実演!
 SUN STAGEの大舞台に立ったROTH BART BARONやフジファブリック、KIRINJIといったバンドたちの上質かつダイナミックな演奏もすばらしかった。"フォーク"や"民謡"といった音楽のありようを現代に再定義するエネルギーを持った出演者が多い『FUJI & SUN』の一つの方向性を体現していたROTH BART BARONの壮大なパフォーマンス。
SUN STAGEの大舞台に立ったROTH BART BARONやフジファブリック、KIRINJIといったバンドたちの上質かつダイナミックな演奏もすばらしかった。"フォーク"や"民謡"といった音楽のありようを現代に再定義するエネルギーを持った出演者が多い『FUJI & SUN』の一つの方向性を体現していたROTH BART BARONの壮大なパフォーマンス。
 KIRINJIは堀込高樹に加え、ボーカルとしてもフィーチャーされたマイカ・ルブテ(キーボード)やBREIMENの菅野颯(ドラムス)、シンリズム(ギター)などが参加したフレッシュなバンド編成で、みずみずしさと円熟した色気が融和したすばらしい演奏を響かせる。
KIRINJIは堀込高樹に加え、ボーカルとしてもフィーチャーされたマイカ・ルブテ(キーボード)やBREIMENの菅野颯(ドラムス)、シンリズム(ギター)などが参加したフレッシュなバンド編成で、みずみずしさと円熟した色気が融和したすばらしい演奏を響かせる。
 サウンドチェックで「夜明けのBEAT」を披露し、始まる前から観客を沸かせたフジファブリックは、曇天空のもとで演奏を開始しながらも、「光あれ」が演奏されるのとまさに同じタイミングで空から光が差し始めたのだから、まさに、野外フェスならではの奇跡!
サウンドチェックで「夜明けのBEAT」を披露し、始まる前から観客を沸かせたフジファブリックは、曇天空のもとで演奏を開始しながらも、「光あれ」が演奏されるのとまさに同じタイミングで空から光が差し始めたのだから、まさに、野外フェスならではの奇跡!
 MOON STAGE出演アーティストたちの、観る者を没入させるような演奏ももちろん忘れがたい。その音の心地よさに「もうずっとこの場から離れたくない」と思わされたOLAibi × U-zhaan + 大友良英の特別編成ライブ。U-zhaanの奏でるビートとOLAibiが発する言葉が出会い、そこに大友のギターノイズが重なり――そうして生み出される上質な熱。音楽とは「出会い」であるという原初的な感覚がそこにはあった。
MOON STAGE出演アーティストたちの、観る者を没入させるような演奏ももちろん忘れがたい。その音の心地よさに「もうずっとこの場から離れたくない」と思わされたOLAibi × U-zhaan + 大友良英の特別編成ライブ。U-zhaanの奏でるビートとOLAibiが発する言葉が出会い、そこに大友のギターノイズが重なり――そうして生み出される上質な熱。音楽とは「出会い」であるという原初的な感覚がそこにはあった。
 Salyuは、「salyu × salyu」名義の名作アルバム『s(o)un(d)beams』の世界に通じる、豊潤なコーラスワークによって「声」と「音」の無限の可能性を体現するようなステージングを披露。声の重なりやハンドクラップなどを駆使して生み出されるミニマムだが広大な音楽世界が圧巻。
Salyuは、「salyu × salyu」名義の名作アルバム『s(o)un(d)beams』の世界に通じる、豊潤なコーラスワークによって「声」と「音」の無限の可能性を体現するようなステージングを披露。声の重なりやハンドクラップなどを駆使して生み出されるミニマムだが広大な音楽世界が圧巻。
 TOP DOCA、Akie、悪魔の沼、AKIRAM ENといったSTONE STAGE出演者たちが作り出した小宇宙のような空間も、このフェスの空間全体に深みと奥行きを与えていたといえるだろう。
TOP DOCA、Akie、悪魔の沼、AKIRAM ENといったSTONE STAGE出演者たちが作り出した小宇宙のような空間も、このフェスの空間全体に深みと奥行きを与えていたといえるだろう。
 日も暮れてすっかり暗くなった中、落ち着いた弾き語りで優しさに満ちた空間を生み出した青葉市子。彼女が演奏する「いきのこり ぼくら」を聴きながら、そういえば、ROTH BART BARONの三船雅也やフジファブリックの山内総一郎もこの日、MCで「生き延びた」「生きること」といった言葉を発していたことを思い出した。
日も暮れてすっかり暗くなった中、落ち着いた弾き語りで優しさに満ちた空間を生み出した青葉市子。彼女が演奏する「いきのこり ぼくら」を聴きながら、そういえば、ROTH BART BARONの三船雅也やフジファブリックの山内総一郎もこの日、MCで「生き延びた」「生きること」といった言葉を発していたことを思い出した。
 SUN STAGEトリの渡辺貞夫グループ。ステージの背後で回るミラーボールとステージ上の派手な照明に彩られる中で披露される情熱的な演奏は圧巻だったが、特に、最後に披露されたジョン・レノン「Imagine」のカバーには、この混沌とした世界に向けられた「祈り」を感じた。音楽フェスという祝祭を、なぜ、私たちは求め続けてきたのか――その理由の一つを、この日の「Imagine」はあらためて分からせくれたように思う。
SUN STAGEトリの渡辺貞夫グループ。ステージの背後で回るミラーボールとステージ上の派手な照明に彩られる中で披露される情熱的な演奏は圧巻だったが、特に、最後に披露されたジョン・レノン「Imagine」のカバーには、この混沌とした世界に向けられた「祈り」を感じた。音楽フェスという祝祭を、なぜ、私たちは求め続けてきたのか――その理由の一つを、この日の「Imagine」はあらためて分からせくれたように思う。
 1日目の夜、渡辺貞夫グループのステージ終了後にキャンプサイト宿泊者向けに行なわれた川村亘平斎 (滞空時間)の切り絵と音楽を組み合わせた、前衛的な、だが不思議と人懐っこいパフォーマンスの記憶も残る中、2日目へ。
1日目の夜、渡辺貞夫グループのステージ終了後にキャンプサイト宿泊者向けに行なわれた川村亘平斎 (滞空時間)の切り絵と音楽を組み合わせた、前衛的な、だが不思議と人懐っこいパフォーマンスの記憶も残る中、2日目へ。
 MOON STAGEトップバッターのAJATEのユーフォリックな演奏で楽しく目を覚ましたかと思えば...
MOON STAGEトップバッターのAJATEのユーフォリックな演奏で楽しく目を覚ましたかと思えば...
 SUN STAGEでの踊ってばかりの国の強烈な演奏に目を見開かされる。今や日本の野外フェスに引っ張りだこの彼らだが、美しいメロディーもドープなサイケデリアも魔法のように生み出してみせるその威風堂々とした演奏は、もはや貫禄すら感じさせるものだ。
SUN STAGEでの踊ってばかりの国の強烈な演奏に目を見開かされる。今や日本の野外フェスに引っ張りだこの彼らだが、美しいメロディーもドープなサイケデリアも魔法のように生み出してみせるその威風堂々とした演奏は、もはや貫禄すら感じさせるものだ。
 そんな踊ってばかりの国の盟友ともいえるGEZANの、高揚感と熱気に満ちた――しかし暑苦しくはない――演奏。「サード・サマー・オブ・ラブ」とマヒトゥ・ザ・ピーポーが紹介していた新曲は、コロナ禍以降の時代感覚を捉えようとして生み出されたのだろう。浮遊感の中にも、沸々とたぎるような静かな衝動が伝わってきた。
そんな踊ってばかりの国の盟友ともいえるGEZANの、高揚感と熱気に満ちた――しかし暑苦しくはない――演奏。「サード・サマー・オブ・ラブ」とマヒトゥ・ザ・ピーポーが紹介していた新曲は、コロナ禍以降の時代感覚を捉えようとして生み出されたのだろう。浮遊感の中にも、沸々とたぎるような静かな衝動が伝わってきた。
 MOON STAGEでは、メンバーにハープがいる新鋭バンド んoon(フーン)がパワフルな演奏を披露している。「ハープがいる」と書くと静かなバンドなのかと想像されるかもしれないが、その演奏はどこまでもグルービーでアグレッシブ。ジャンルの壁も価値観の壁も突破していくようなパンキッシュさすら感じさせるパフォーマンスが力強く、たくましい。
MOON STAGEでは、メンバーにハープがいる新鋭バンド んoon(フーン)がパワフルな演奏を披露している。「ハープがいる」と書くと静かなバンドなのかと想像されるかもしれないが、その演奏はどこまでもグルービーでアグレッシブ。ジャンルの壁も価値観の壁も突破していくようなパンキッシュさすら感じさせるパフォーマンスが力強く、たくましい。
 STONE STAGEでどんぐりずが入場規制を出しているのと同時間帯にMOON STAGEに立った角銅真実は、バンドメンバーとともに穏やかで有機的なアンサンブルの中でりんとした歌声を響かせる。角銅自身が誰よりも音との戯れを楽しんでいるんじゃないかと思えてくる、すごみの中にも無邪気さを感じさせる姿に音楽の喜びがひしひしと伝わってきた。
STONE STAGEでどんぐりずが入場規制を出しているのと同時間帯にMOON STAGEに立った角銅真実は、バンドメンバーとともに穏やかで有機的なアンサンブルの中でりんとした歌声を響かせる。角銅自身が誰よりも音との戯れを楽しんでいるんじゃないかと思えてくる、すごみの中にも無邪気さを感じさせる姿に音楽の喜びがひしひしと伝わってきた。
 夫婦漫才のような掛け合いの中で優しく包み込むような音楽を響かせたハンバート ハンバートのパフォーマンスは、笑いと安寧と感動が同時に迫ってくるようだった。「2人」というミニマムな人間同士の関わり合いの中から、こんなにも複雑かつ大きな世界を表現し得ることに震える。そんなハンバート ハンバートをはじめとするMOON STAGE出演者たちのマイペースな姿は、今年の『FUJI & SUN』全体を通して、その空気の中に特筆すべき安らぎと穏やかさを与えていたといえるだろう。
夫婦漫才のような掛け合いの中で優しく包み込むような音楽を響かせたハンバート ハンバートのパフォーマンスは、笑いと安寧と感動が同時に迫ってくるようだった。「2人」というミニマムな人間同士の関わり合いの中から、こんなにも複雑かつ大きな世界を表現し得ることに震える。そんなハンバート ハンバートをはじめとするMOON STAGE出演者たちのマイペースな姿は、今年の『FUJI & SUN』全体を通して、その空気の中に特筆すべき安らぎと穏やかさを与えていたといえるだろう。
 SUN STAGEに登場し、こちらがうなってしまうほどの巧みなステージングで魅せたスチャダラパーは、「今夜はブギー・バック」や「サマージャム'95」といった往年の大名曲も惜しげもなく披露。ロボ宙も参加したそのパフォーマンスは、しなやかかつ軽やかでありつつ、ベテランとしての重みも強く感じさせるものだった。コロナ禍以降の不安によって生まれる人々の心のとげをユーモアで抜いていくような、オーディエンスとのコミュニケーションもみごと。
SUN STAGEに登場し、こちらがうなってしまうほどの巧みなステージングで魅せたスチャダラパーは、「今夜はブギー・バック」や「サマージャム'95」といった往年の大名曲も惜しげもなく披露。ロボ宙も参加したそのパフォーマンスは、しなやかかつ軽やかでありつつ、ベテランとしての重みも強く感じさせるものだった。コロナ禍以降の不安によって生まれる人々の心のとげをユーモアで抜いていくような、オーディエンスとのコミュニケーションもみごと。
 クラブライクだった1日目とは違い、よりライブ寄りだった2日目のSTONE STAGEでは、YOSI HORIKAWA、Hana Hope、INOYAMALAND、どんぐりず、Ramza、DJ KENSEIといったアーティストたちが、独創的なパフォーマンスを披露。INOYAMALANDのような大ベテランもいれば、前述したように入場規制を起こすほどの盛況ぶりを見せたどんぐりずや、弱冠16歳のシンガー・Hana Hopeの清らかな歌声など、若いエナジーが渦巻いた空間でもあった。
クラブライクだった1日目とは違い、よりライブ寄りだった2日目のSTONE STAGEでは、YOSI HORIKAWA、Hana Hope、INOYAMALAND、どんぐりず、Ramza、DJ KENSEIといったアーティストたちが、独創的なパフォーマンスを披露。INOYAMALANDのような大ベテランもいれば、前述したように入場規制を起こすほどの盛況ぶりを見せたどんぐりずや、弱冠16歳のシンガー・Hana Hopeの清らかな歌声など、若いエナジーが渦巻いた空間でもあった。
 そして最後の最後、空が我慢の限界を迎えたかのように降り注ぐ大雨の中で観た大トリ・奥田民生の、ひょうひょうとしつつも力強い弾き語り。1日目が始まる頃には「なんとかしのいだ」と思っていた雨が、奥田民生が演奏を始めた瞬間に、文字通り「バケツをひっくり返したように」降り注いだのだから、さすがに面食らった。「もしかしたらこのまま中止?」という嫌な予感も一瞬よぎったが、無事ライブは続行。奥田自身も若干戸惑っているようだったが、この時点でフェスも最後の最後、「雨もここまで我慢してくれたのだ」と腹をくくるしかない状態で、意を決したようにパワフルな弾き語りを披露。「マシマロ」に始まり、ユニコーンの楽曲、THE YELLOW MONKEY、斉藤和義、ウルフルズのカバー、「イージュー★ライダー」、「さすらい」といった大ヒット曲たち、そして、アンコールの「風は西から」まで、そのマイペースなMCとは裏腹に、魂をぶつけていくような演奏がすさまじかった。
そして最後の最後、空が我慢の限界を迎えたかのように降り注ぐ大雨の中で観た大トリ・奥田民生の、ひょうひょうとしつつも力強い弾き語り。1日目が始まる頃には「なんとかしのいだ」と思っていた雨が、奥田民生が演奏を始めた瞬間に、文字通り「バケツをひっくり返したように」降り注いだのだから、さすがに面食らった。「もしかしたらこのまま中止?」という嫌な予感も一瞬よぎったが、無事ライブは続行。奥田自身も若干戸惑っているようだったが、この時点でフェスも最後の最後、「雨もここまで我慢してくれたのだ」と腹をくくるしかない状態で、意を決したようにパワフルな弾き語りを披露。「マシマロ」に始まり、ユニコーンの楽曲、THE YELLOW MONKEY、斉藤和義、ウルフルズのカバー、「イージュー★ライダー」、「さすらい」といった大ヒット曲たち、そして、アンコールの「風は西から」まで、そのマイペースなMCとは裏腹に、魂をぶつけていくような演奏がすさまじかった。
 初めと終わりに波乱はあれど、今年も「ここ」でしか生まれない空間が広がった『FUJI & SUN』。この2日間における個人的なハイライトシーンを挙げるとしたら、2日目の昼過ぎにこのフェスで最も小さなステージであるSTONE STAGEで観た、INOYAMALANDの演奏中の一幕。SUN STAGEで演奏中のGEZANの演奏がうっすらと遠くに聴こえる中で、この日本のアンビエント音楽界の重鎮的ユニットは、「できることなら、一匹のヒグラシのようになりたい」と語り、そのささやかで濃密な音楽を奏でていた。それはとても幻想的な一場面だった。
初めと終わりに波乱はあれど、今年も「ここ」でしか生まれない空間が広がった『FUJI & SUN』。この2日間における個人的なハイライトシーンを挙げるとしたら、2日目の昼過ぎにこのフェスで最も小さなステージであるSTONE STAGEで観た、INOYAMALANDの演奏中の一幕。SUN STAGEで演奏中のGEZANの演奏がうっすらと遠くに聴こえる中で、この日本のアンビエント音楽界の重鎮的ユニットは、「できることなら、一匹のヒグラシのようになりたい」と語り、そのささやかで濃密な音楽を奏でていた。それはとても幻想的な一場面だった。
 あるいはまた、こんなシーンも印象に残っている。2日目の午前中、踊ってばかりの国が名曲「ghost」を演奏し始めると、私の後ろでお父さんに肩車をされながら見ていた小さな女の子が一緒に歌い始めた。彼女は、このサイケデリックロックバンドの曲の歌詞をしっかりと覚えているようだった。
あるいはまた、こんなシーンも印象に残っている。2日目の午前中、踊ってばかりの国が名曲「ghost」を演奏し始めると、私の後ろでお父さんに肩車をされながら見ていた小さな女の子が一緒に歌い始めた。彼女は、このサイケデリックロックバンドの曲の歌詞をしっかりと覚えているようだった。
一匹のヒグラシに憧れる求道者のような音楽家が奏でる音、ロックバンドの演奏の中でも鮮明に聴こえてきた少女の歌声――これらの光景は私にとって、この『FUJI & SUN』という空間の特別さを物語るのにふさわしい、記憶に刻まれたものだ。
以下に、『FUJI & SUN』をプロデュースしたWOWOW事業局事業部・前田裕介プロデューサーのインタビューをお送りする。インタビューは1日目を終え、2日目が今まさに始まろうとしている朝に行なった。
前田裕介プロデューサーインタビュー
 ――『FUJI & SUN '22』1日目を終えられて、これから2日目が始まろうとしていますが一昨日から昨日の朝にかけては雨が大変だったようで。
――『FUJI & SUN '22』1日目を終えられて、これから2日目が始まろうとしていますが一昨日から昨日の朝にかけては雨が大変だったようで。
そうなんです。昨日の夜中の3時にホテルのドアをたたかれて、「ステージが吹っ飛びそうです。至急来てください」と聞かされました(苦笑)。1年に1度あるかないかの強風が、まさかの前日に来てしまって。
――そんな中でも無事に開催できてよかったです。あらためて、この『FUJI & SUN』がどのようなコンセプトから生まれたフェスなのか、教えていただけますか?
「キャンプフェスを立ち上げたい」という事業局から出てきたアイデアが始まりでした。「WOWOWらしいフェスってどういうものだろう?」と考えたときに、そもそもWOWOWは映画・音楽・スポーツ・舞台などのジャンルをクロスオーバーして放送している局である。そういう部分をフェス上でも再現できないかと。そこでまずは、音楽とアクティビティ、そして映画を軸としながらキュレーションして、それぞれのジャンルが有機的に絡まるようなフェスにできないかというコンセプトが立ち上がっていきました。
――ジャンルの絡み合いというのは、まさに出演ミュージシャンの面子にも表われていますよね。
そうですね。初年度はエルメート・パスコアールというブラジル音楽界の巨匠や、デトロイトハウスの重鎮であるセオ・パリッシュが来てくれて、矢野顕子さんやcero、Charaさんもいた。2回目も、大貫妙子さんがいればくるりや森山直太朗さんもいるし、折坂悠太さんやカネコアヤノさんもいて。ジャズがあればヒップホップもロックもあるし、レジェンドもいれば若手アーティストもいる。そうやってジャンルと世代がクロスオーバーしたものにしたいというのは、一貫してテーマとしてありました。今年も、渡辺貞夫さんがいれば、んoonのような若手もいて、GEZANもいるし、スチャダラパーもいるし、フジファブリックもいる。
――多岐にわたる面子ですよね。
初年度に海外のアーティストがいたのも、すごくWOWOWらしいと思います。WOWOWはグラミー賞もアカデミー賞もやっているし、洋画も邦画もやっている。ドメスティックなものだけを紹介してきたわけではないので。ただ、いかんせん2回目以降はコロナ禍になって、海外のアーティストが呼びづらい状況が続いてしまって......。いつかはまた、海外のアーティストを呼べる状況に戻したいです。邦洋のいろんなジャンルのアーティストがクロスオーバーするフェスになればいいなと思っています。
――ブッキング以外の面でも、コロナ禍以降でフェスの運営に難しさを感じる場面が多いと思うのですが、音楽以外の部分では、これまで『FUJI & SUN』はどのように変化してきましたか?
まず初年度は、当時映画部の担当がスタジオジブリと懇意にしていたことや、『かぐや姫の物語』の舞台が富士市だったこともあり、ジブリさんに相談して映画上映もやらせていただいたんですけど、映画に関しても新型コロナウイルスの影響で諦めざるを得なくなってしまって。ただその分、キャンプの要素は回を重ねるごとに強くなっていると思います。キャンプエリアも拡大していますし、日本最大級のキャンプメディア「CAMP HACK」さんや「hinata」さんといったWEBメディア、そして「SWEN」さんという静岡県で地位のあるアウトドアショップに初年度から出店していただいている中で、今年は「CAMP HACK」とコラボレーションという形で「UZD」さんというリユースアウトドアギアショップにも出店していただいたり、昨年に続き「ジャーナル スタンダード」さんには、福岡で期間限定出店している「Yoo Hoo store」というアウトドアショップを、『FUJI & SUN』会場内に特別に出店していただきました。
また「CAMP HACK」さんとは、スチャダラパーのBoseさん、森山直太朗さん、レキシさんをMCに迎えて「音楽」と「キャンプ」を楽しむ番組「CAMP TV」を昨年立ち上げました。そこに奥田民生さんにゲスト出演していただいたことが、今回の『FUJI & SUN』の出演につながったり、レギュラー番組とリアルイベントの両方をプロデュースしているWOWOWならではの展開が生まれています。
――前田さんご自身はキャンプをやられるんですか?
昨年初めてキャンプデビューしました。豊富なギアのおかげで、もともとインドア派の自分でも快適に楽しくキャンプできることが分かり、順調に沼にはまりつつあります。自分で実際にやってみて見えてきたことなんですけど、『FUJI & SUN』には、かなり深いところまでキャンプというジャンルを掘っているお客さんが来てくれているんですよね。こういう状況もすごくWOWOWっぽいなと思いました。具体的に説明すると、WOWOWは、映画でも「ジム・ジャームッシュ特集」とか、「マーティン・スコセッシ特集」といった特集をよくやりますけど、そのジャンルに深く愛されるものをフィーチャーしていくのが、すごくWOWOWらしい部分だと思うんです。それが『FUJI & SUN』ではキャンプでも起こっているし、音楽でも起こっている。青葉市子さんやGEZANって、お茶の間のゴールデンタイムとかで流れまくっているような音楽ではないけど、音楽に思い入れがあって、熱量を持って掘っていくような人が好きになるミュージシャンですよね。そういう人たちが出ているからこそ、感度が高かったり、そのジャンルを深掘りしている人たちが集まってくる。そこで例えば、キャンプが目的で来た人が、たまたま見たGEZANの大ファンになる、みたいなことがありえるわけで。

――まさに最初に仰った「キュレーション」ということですよね。そこがやはり『FUJI & SUN』においては重要であると......。
WOWOWのプロデューサーは、みんなキュレーターだと思うんです。WOWOWは日本で初めて『ツイン・ピークス』を放送した局ですけど、「『ツイン・ピークス』ってなんぞや?」という時期に、「こういうドラマがアメリカにあるんだよ」と紹介した。錦織圭選手や大坂なおみ選手が活躍する前のテニスだったり、ボクシングもそう。WOWOWはそういう放送局だし、『FUJI & SUN』はそのリアル版だと思いますね。われわれの目利き、放送で体現してきたことを、リアルの場で作れたら理想だなと。もちろん、時間はかかると思います。即効性を求めたり、プロモーションにおいては技が必要になってきますけど、それでも辛抱強く、収支などもちゃんと意識しながらやっていくと、数年後には、無敵のフェスになれるんじゃないかと思っています。
――そうやって時間をかけて成熟していったフェスは、お客さんとの関係性も特別なものになりそうですね。
理想としては、『森、道、市場』のようになればいいなと。このフェスのすごいところって、「このヘッドライナーがいるから行きます」とかじゃなくて、「このフェスに行きたい」という気持ちでお客さんが集まっているところなんですよね。それができるのは、出店の面白さや空間の気持ちよさがそこにあるからだし、アーティストの選出にも信頼があるからだと思う。「空間」を信頼して集まってくれる人が増えてほしい。そうやって、結果的に「『FUJI & SUN』っていいよね」と思ってもらって、『FUJI & SUN』のファンが集うコミュニティが生まれればいいなと思います。コミュニティって、偏愛を持った人たちの集合体だと思うんです。だからこそ、ガワを作って「来てください」みたいな力技ではなくて、ボトムから段々と上げていかないといけない。
――1日目では、「MOON STAGE」のトークセッションで富士市の小長井市長が太鼓をたたく場面があって驚きました。地元とのコミュニケーションに関してはどのような意識を持っていますか?
そこは僕らも勉強させてもらいながらやっています。運営には、インフュージョンデザインという会社に入っていただいているんですけど、彼らは日本のいろんなフェスを立ち上げてきた人たちなんです。彼らから出たワードに「地元」があって、「地元を大事にしないと祭りは続きませんよ」という話をしてもらいました。それって、最初から頭では分かっていたことだけど、こうやって何年も富士市の地元の人たちと一緒にフェスを作ってくると、本当に腹落ちします。それは市長や市役所の方々とのやりとりもそうですし、ボランティアスタッフの方々ともそうです。彼らは自分たちの地元で『FUJI ROCK』のような地元に愛されるフェスを育てたいと思って助けてくれていると思うし、そういう気持ちを持ってくれている人たちとちゃんとコミュニケーションを続けていくことで、祭りの持続性が保たれていく。昨日の朝、会場に行くときに乗ったタクシーの運転手さんが、「最近、コロナで仕事なくて」っておっしゃっていたんですけど、「でも、日曜日にアーティストの送迎の仕事をやらせてもらうんで、ありがたいです」という話をしてくださって。小さな話ではありますが、具体的なそういった声を聞けると、その一つ一つの声を大事にしながら、積み重ねていくことが大事なんだろうなとあらためて気付きます。やり逃げじゃなくて、その土地でみんなと一緒に共生しながらフェスを成長させていくって、どういうことなのか。そういうことにはちゃんと向き合っていきたいです。
――前田さん個人として、お客さんという立場でもさまざまなフェス体験があると思うのですが、前田さんにとって音楽フェスってどういうものですか?
若い子たちによくマウンティングするのは、1997年の『FUJI ROCK』に行ったということ(笑)。当時大学生だったんですけど、そこで観たRage Against the Machineのライブが僕の生涯のベストライブです。大学の友人と一緒に車で音楽を聴きながら会場に行って......大変でしたけどね。あれはまさに2日目が台風で中止になってしまいましたから。でも、すごくいい原体験でした。その後、『メタモルフォーゼ』や『TAICOCULB』、『森、道、市場』のようなアンダーグラウンドに近いフェスも体感したことで、「自分が目指すのは、マスとアングラの間なのかもな」と思うようになりました。それが今の『FUJI & SUN』につながっているような気がします。
音楽を中心としたカルチャーが好きでWOWOWに入社して、音楽番組を作って、社内外でさまざまな偏愛を持つ人と知り合って、今はフェスというイベントに携わっていることに縁を感じています。数々のカルチャーをキュレーションしてきたWOWOWの強みを活かしながら、これまでのどのフェスとも違う、"『FUJI & SUN』のファン"に愛されるフェスに育てていきたいですね。
 <番組HP>
<番組HP>
■FUJI & SUN '22 <7月17日 (日)午後9:00> WOWOWライブ
https://www.wowow.co.jp/detail/181043
<イベントHP>
https://fjsn.jp/
取材・文/天野史彬