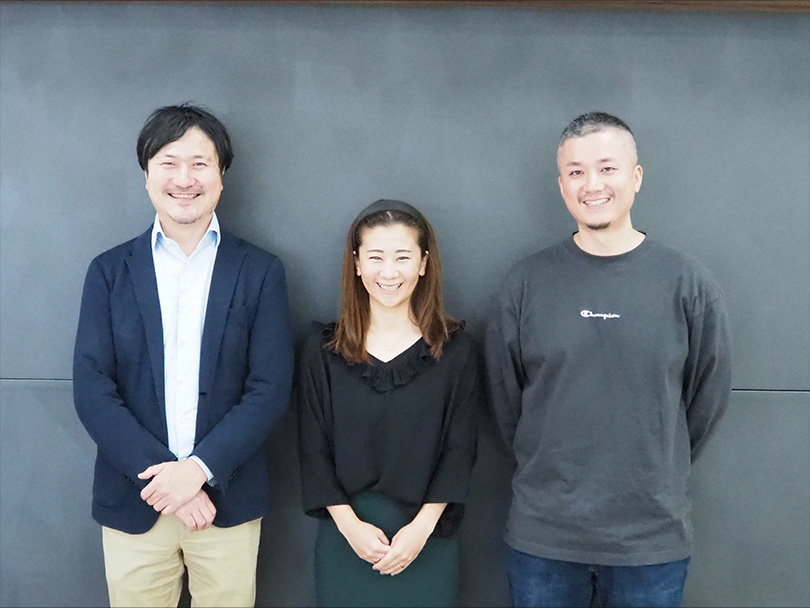斎藤工の映画愛の根幹は「面白いものをシェアしたい」という思い――「映画工房」での8年が与えてくれたもの -斎藤工【前篇】
俳優、映画監督、プロデューサー:斎藤工

芸能界きってのシネフィルとして知られ、いまや俳優としてのみならず、監督、プロデューサー、移動映画館「cinéma birdシネマバード」の運営など、様々な立場で映画に携わり続ける斎藤工。実は、そんな斎藤さんとWOWOWの映画番組のつながりはかなり長い。 2010年の年末の情報番組「ザ・ムービー・ニュース2010」を皮切りに、2011年4月より映画紹介番組「シネマNAVI」にレギュラー出演。その後継番組として「映画工房」が2011年10月に始まり、翌2012年10月には、映画通のゲストを迎えて隠れた名作を紹介する「隠れた名作"発掘良品"」もスタート。「映画工房」は今年放送400回を迎えた。
今回、斎藤さんにロングインタビューを敢行。【前編】【後編】の2回に分けて、"映画人"斎藤さんの映画との関わり、WOWOWの番組への思い、さらには日本映画界の発展のための提言など、ここでしか聞けない貴重なお話を伺った。
「ウルトラマン」がつないだ父と息子
――斎藤さんがここまで映画好きとなったきっかけですが、映像業界で仕事をしてこられたお父さまの影響がかなり大きかったと伺っております。
そうですね。今度『シン・ウルトラマン』(企画・脚本:庵野秀明/監督:樋口真嗣)という作品に出演させていただくのですが、実はうちの父は、映像業界に入る前に円谷プロダクションでバイトをしていて『ウルトラマンタロウ』の時に爆破とかを担当していたそうなんです。その後、『修羅雪姫』(1973年)などで知られる藤田敏八監督の現場に入ったそうなのですが、父の業界の入口が円谷だったと知って、そういえば、子どもの頃にウルトラ怪獣の人形とかがあったなと思い出しました。
先日まで万田邦敏監督の現場にも参加していたのですが、やはり昔、父と万田さんは一緒にドキュメンタリーを作ったり、以前、在籍されていたところから独立して、父と万田さんは映像制作会社を作って、学校用の性教育のビデオを作ったり、万博の映像を一緒に作ったりしていたそうで。
僕自身は父の存在をそこまで意識してはいなかったのですが、結果的にめぐりめぐって2世代での関わり、接点が生まれているのは不思議な感じがします。宿命のような何かが宿っていたような気がしますね。
――子どもの頃からお父さまの映画の"英才教育"を受けてきたと言えますね。
そう言うと父は喜ぶかもしれませんが(笑)、僕自身はわりと普通の映画が好きで、クセのある作品や父が好む古典映画が心に響いていたかと言うと、刺さってないものもたくさんあります。好きな映画を聞かれると、よく小津安二郎監督の『お早よう』を挙げさせていただいていますが、小津監督の名前も知らない頃に見て、オナラを題材にしているのが子どもながらに面白かった記憶があるんです。父の思惑はわかりませんが、僕の心に引っかかったのは、造詣が深い作品というよりもシンプルなものが多かった気がします。
ただ、連載をさせていただいている雑誌「映画秘宝」の人たちやWOWOWで映画の話をする時など、共通言語となっているような作品――普通は出会わないような作品を自分も見ていたという思いはあって、それは父のおかげだったのかなと。

父は古典ばかりでなく『トレマーズ』とか『ヒドゥン』といった娯楽作品も好んで見せてくれて、僕もそういう作品がすごく面白かったし、周りの友達が「週刊少年ジャンプ」にハマっている時期に、僕はそういう映画を見ていました。
初めてできた彼女とのデートに母がくれた映画のチケットは...?
――今年7月の「映画工房」では、「映画に出会う! 没後50年 成瀬巳喜男監督特集」を紹介しました。その時斎藤さんに成瀬作品を1本選んでいただきましたが、代表作と言われる『浮雲』ではなく、『乱れる』を挙げてくださいました。
うちの父も母も『乱れる』が大好きでして。『浮雲』に関しては、自分が出演した『昼顔』というドラマの劇場版の際に、キーワードとして西谷弘監督、脚本の井上由美子さんとも話をさせていただいたんです。単なる"不倫"じゃなく、昔の日本映画にあった、男女の逃れられない渦のような欲望――日本人の中にある、それをちょっと上品に描く残酷さみたいなものが合うんじゃないかと。
ただ、僕自身が成瀬監督にグッとハマり込んだきっかけは『乱れる』で、若い世代の娯楽としての成瀬作品の入口は『浮雲』より『乱れる』の方がいいんじゃないかと思いました。
――お父さまだけでなく、お母さまもかなりの映画好きなんですね?
そうですね。母は、ペドロ・アルモドバルとかが好きで。僕に初めて彼女ができたときに『ライブ・フレッシュ』のチケットをくれて「彼女と行きなさい」と(笑)。
――ペネロペ・クルスやハビエル・バルデムらも出演している、ミステリアスな愛憎劇ですね。デートムービーとしては...大丈夫だったんでしょうか(笑)?
当時の彼女は年上だったんですけど、彼氏の母からのメッセージをどう捉えたのか...。困惑してましたよね(苦笑)。母は父とはまた違った映画の嗜好があって、やはり、あの父と結婚するだけあるなぁと思うんですが(笑)。
俳優兼監督の思いーー「役者じゃなきゃ撮れない映画があるはず!」
――その後、斎藤さんは俳優としてこの世界に足を踏み入れます。お父さまから「映画は机の上で学ぶものじゃない。お前は一刻も早く現場に出ろ」と言われたそうですが、そこで選んだのが監督や制作スタッフの側ではなく、役者だったんですね?
そうですね。「現場に出る」ということを考えたとき、例えばどこかの監督の組であったり、職人さん的なスタッフの門下生になるという発想にはならなかったんです。なんででしょうね...? 映画づくりの裏側に関して、父の現場を見ていたとはいえ、「表から」というか、正面から行ったという感じはありました。
ただ、これは監督をするようになった今だからこそ、感じたことですが、役者じゃなきゃ撮れない映画がある気がしていて、その部分を強調していかないと、表現者として汗をかいていないのに「いい映画ってこんな感じでしょ?」という、すごく表層的な映画を撮ってしまうんじゃないかという恐れが未だにあります。
役者としていろんな監督の現場づくりも見てきたし、役者として役者さんとどう付き合うか? ということを突き詰めていかないと、自分が作る必然がなく、ただの記念で終わってしまうという懸念があります。
逆に言うと、それは映画づくりを続けていかないと立証できないんです。いま仕上げている作品で、(監督作品が)11本目になるんですが、今後も作り続けていこうと強く思っています。
ただ「監督」という関わり方が自分に一番フィットしてるかと言うと、そんな確証はまだ全然ありません。(「映画工房」の協力を得て製作され、斎藤さんが企画・原案・脚本を担当、声の出演を担当した)『映画の妖精 フィルとムー』のような作品もあるし、今度、公開される映画『MANRIKI』は、(主演に加えて)プロデューサーという立場で参加していますが、芸人の永野さんとの雑談から立ち上げて「これは形にしたらとんでもないものになる」と思って企画しました。

「映画の妖精 フィルとムー」
「日常」にこそ実はクリエイティブのヒントがある
――全方位的な立場で映画に関わられていますね。
そもそもの始まりとしては、「面白い映画をシェアしたい」という思いからなんです。映画の旨味って人とシェアすることで初めて自分に返ってくるものだと思うんです。咀嚼したものがストンと消化されるといいますか。父や母と1本の映画について、それぞれの見解を持ちつつ、大皿のおかずをシェアするような感覚で映画を見てきたことが、ここにつながっているんだと思います。

もっと言うと、WOWOWさんからいただいた、この8年の時間が、僕の映画づくりや映画とのこうした関わり方の背中を押してくれている部分は間違いなくあると思います。自分のクリエイティブを発揮したいというより、面白いものをシェアしたいし、役者や音楽をつけてくれる人たちの才能を多くの人に見せたい、自慢したいという観点はゆるぎなくあって。
番組で映画を紹介している時と、自分の映画を作っている時の感覚って、「あぁ、ここがこの映画の旨味だな」という切り取り方は実はすごく似ているんです。僕が尊敬する映画人の佐藤佐吉さんが「1本映画を見れば、いいところ、盗みたくなるようなところが絶対にある。それは監督が見ても、脚本家が見ても役者が見てもあるもので、100本の映画を見れば100の武器が備わる」ということをおっしゃっていて、全くその通りだと思うし、僕は、そのための映画メモを作っています。
――見た映画に関して必ずメモを残してるんですね。手書きですか? それともスマホやタブレットに?
両方ですね。例えば「映画工房」で紹介するとき、初めて見る作品も多いし、面白いかどうかだけじゃなく、その映画にしかない"強度"みたいなものが必ずあるんです。それを忘れないようにしないと意味がないし、人に届けられないと思って「いいシーン」「いい演出」「いいお芝居」といった感じでジャンル分けして残すようにしています。
自分で映画を作るときにメモを見直すのですが、「これいいな」って気づきがあったりするんです。要は、自分の心がどこで動いたのか? 自分自身のものの見方につながってくるし、スタッフに「あの映画のあのシーンの感じで」という具合に、感覚のシェアが言葉や絵コンテなしで共有できるとすごく強いんです。
新海誠監督は、日々ロケハンをしているそうで、目的を持ってどこかに行ってその風景を撮るというより、日常で心が動いた景色に対して必ずシャッターを切るようにして、それを元に絵コンテを作っていくそうなんです。
僕も日々、スマホで実景撮りをしていて、最初から用途があるわけではなく、飛行機の上空からの風景やハロウィンの渋谷の交差点のど真ん中など、特殊なシチュエーションを撮って、いつかそれが何かで使えたらと思っています。芝居もそうですけど、日常にこそ実はヒントがあるんだなと。
最近、見る映画、出る映画が全部つながってきているなとより強く感じています。それは、昔から父と映画を見てきた時間以上にいま、こうやって番組などを通じて、映画を見て紹介するパブリックな環境を与えていただいて、強みになっていると感じています。
斎藤さんが日本の映画界やエンターテイメントの現状に抱く危機感の本質とは――?
インタビュー【後編】では、エンタメ業界への愛ある厳しい提言と新たな提案、さらに今後、斎藤さんがWOWOWを通じて実現したい大きな夢なども語ってもらった。
聞き手/WOWOW映画部 小野秀樹
構成/黒豆直樹 撮影/祭貴義道 制作/iD inc.