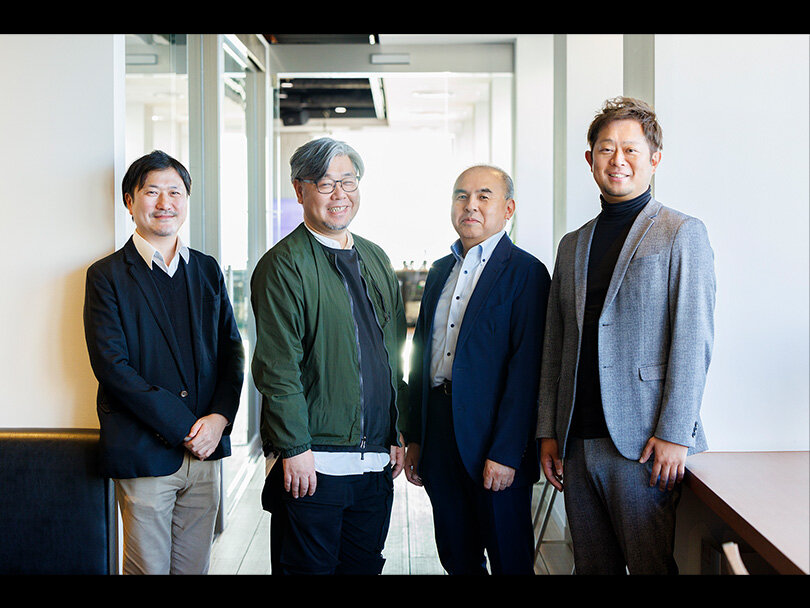「ヒットする作品には"秘密の共有"という共通点がある」――『太陽は動かない』羽住英一郎監督がたくさんの人に見てもらえる作品づくりを語る!
「太陽は動かない」監督 羽住英一郎

WOWOWが藤原竜也&竹内涼真を初共演で迎え、過去最大級のスケールで劇場版映画と連続ドラマを同時に制作する超巨大プロジェクトがついにそのベールを脱ぐ! 人気作家・吉田修一が手がけた、凄腕の産業スパイを主人公にした同名のハードボイルド小説、および主人公の若き日を描いた『森は知っている』の2冊を原作とした映画『太陽は動かない』の公開に加え、吉田修一監修の下、映画の主要キャラクターや設定はそのままに、オリジナル脚本で作り上げられた連続ドラマW『太陽は動かない -THE ECLIPSE-』が放送される。劇場版は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、公開延期が決まったが、連続ドラマは当初の予定通り5月24日(日)よりスタートする。
監督を務めるのは『海猿』シリーズなどのヒット作を世に送り出し、WOWOWとTBSの共同制作作品『ダブルフェイス』、『MOZU』も手掛けた羽住英一郎。新たな作品を作るたびに、日本映画の枠組みを大きく広げてきたこの男にとって、今回の『太陽は動かない』プロジェクトはどのような挑戦だったのか? ブルガリアでの大規模なロケも行われた撮影の様子なども含め、じっくりと話を聞いた。
「日本映画だから」という意識は最初から持っていない!
――まずは監督の仕事観などについて伺います。そもそも監督が映画づくりを志したきっかけは?
僕が小学生の頃って土曜日まで学校があったので、土曜日に学校の図書室で江戸川乱歩の小説を借りて、夜更かしして読むのが好きだったんです。このワクワク感を自分も作るようになりたいと思って、当時は小説家になりたいと思っていました。当時は「エンタメ」という言葉を知らなかったんですが、いま思うとやりたかったのは「エンターテインメント」を作ることだったんでしょうね。このドキドキ感とワクワク感をいろんな人に味わわせたいなという思いでした。
中学生になって『第三の男』という映画を有楽町の地下の名画座に見に行き、そこで「これだ!」と思いました。ストーリーがあって、音楽もあって、俳優の芝居やライティングも完璧なんです。「あぁ、自分がやりたかったのはこれだ」と思ってそこから映画を志すようになりました。
――『海猿』シリーズに『MOZU』、そして今回お話を伺う『太陽は動かない』も含め、スケールの大きな作品を作られてきましたが、ハリウッド大作に追いつきたいという思い、日本のエンターテインメントの限界値を広げたいという意識はご自身でもお持ちなのでしょうか?
初めて自分でちゃんと映画館に見に行った映画が『エアポート'75』だったり、そもそもハリウッド映画を見て育って、エンタメ大作、パニックムービーが好きなんですね。だから映画監督を目指すようになってからも、あまり「日本映画」という意識がなかったんですよ。別に「ハリウッドに行く」と思っていたわけでもないんですが。
いまだに自分で脚本に関わっているときも、なんとなくトム・クルーズがしゃべっているようなイメージで作っていたりするんです(笑)。話の運び方だったり、画のイメージに関しても、自然と自分が見て育ったハリウッド映画の感覚でやっていて、「日本映画だから...」という意識がないのだと思います。

いかに企画を通すか? 用意周到にヒットに導きシリーズ化を勝ちとった『海猿』!
――日本映画の予算規模で、実現できる企画、できないものもあるかと思います。監督ご自身が、やりたい企画を実現させるために大切にしていること、意識していることはどんなことですか?
ヒットさせること...と言っても、ヒットさせようと思ってヒットさせるのは難しいですが(笑)。あとはやはり、みんなが楽しめないと意味がないんですよね。
僕にとっては長編映画デビュー作が『海猿 ウミザル』(2004年)だったんですが、既に原作の漫画は連載は終了していたんですね。当時はそこまでメジャーな原作ではなかったんですが、生死にかかわるようなスペクタクルな描写がたくさんあり、予算が限られていて、最初はフェリーの遭難事故のプロットを作ったんですが、予算的に無理だったんですね。
しょうがないので1作目は潜水士たちの訓練の話にして、それをヒットさせた上で、(よりスケールの大きな)人命救助の物語を描くことにしようという発想で進めていきました。幸運なことにヒットしてシリーズ化されましたが、最初の頃は周りから「羽住、デビューするの? 『海猿』やるんだって?」と言われても「あぁ、きっとこの人の頭の中の『海猿』って巨大なフェリーが出てきて...という感じなんだろうなぁ」と。なんだか「あの人と付き合ってるんだって?」と言われつつ、実はまだ手も握ったことがないような居心地の悪さを感じていました(笑)。
ただ、そうやって最初にきちんとヒットさせて、そこから徐々に広げていくということはイメージとして持っていました。どうしたらヒットさせて、次につなげられるか? 『暗殺教室』の時も同じで、最初は続編の制作は決まってなかったんですが、僕としては当然、ヒットさせてきちんと『卒業編』で完結させたいと考えていました。

――先ほども「ヒットさせようと思ってさせるのは難しい」とおっしゃっていましたが、羽住監督が考えるヒットさせるために必要な要素とは何でしょうか?
そうですね、ヒットする映画が共通して持っているのは「秘密の共有」なのかなと思いますね。映画を見た人が知ってしまったことを、口に出して言ってしまうとその感動が伝わらないと思うと、自然と言わなくなって、代わりに「見てみなよ」と言うようになるんですよね。
「あの映画、見たの? どうだった?」と聞かれた時、つまんなかったら1から10まで全部言っちゃうものなんですよ(笑)。でもそこで、何か感動したポイントがあって、それを自分の言葉では伝えきれないと思ったら「見てみなよ」となるんです。そうやって言葉では伝えきれない感動がある時に、口コミで広がっていくんだろうと思います。
僕自身、助監督時代に『踊る大捜査線』の劇場版1作目(『踊る大捜査線 THE MOVIE』)に参加したのですが、みんなに「青島、どうなるの? 死んじゃうの?」と聞かれ、「いや、実は...」と口で説明しても、劇場で感じるあの感動は絶対に伝わらないので「いや、見てみなよ」と言っていました。そういうものがヒットする映画にはあると思いますし、『海猿』の2作目はそのあたりを僕自身も意識しました。
分厚い2冊の原作を1本の映画に ハードボイルド×青春物語の化学反応に勝算アリ!
――それでは今回の「太陽は動かない」についてお聞きしていきます。そもそも原作者の吉田修一さんが『太陽は動かない』に関しては「羽住さんに実写化してもらいたい」とおっしゃっていたそうですね。
お話をいただいて、既に『森は知っている』も発売されていたので両方を読んでみたんですが、『太陽は動かない』だけだとちょっと物足りないというか、物語として派手ではあるんですが『森は知っている』があることでグッとくる部分があるので、なんとか両方を映像化できないかなと思ったんですね。

――『太陽は動かない』は次世代エネルギーをテーマに、産業スパイ・鷹野一彦が活躍する物語であり、『森は知っている』は鷹野が南の島で過ごした17歳の頃の青春を描いた物語ですね。
2つの物語で年代が異なるため、そうするとキャストも変わってしまうので、どうやったら実際に形にできるのかと考えていたんですが、そんな時にちょうどWOWOWの武田プロデューサー(TBSでの"映画武者修行"がWOWOWにもたらした新たなDNAとは? 連続ドラマW『悪党 ~加害者追跡調査~』武田吉孝プロデューサーインタビュー)とお話をする機会があったんです。
当時は「別々の2本の映画にするしかないかな」と思っていましたが、武田さんに「2冊の原作をまとめて1本の映画にすればいいんじゃないか?」という話をいただいて正直、それは目から鱗でした。
それまではボンヤリと「これはどうやったら映画にできるかな?」という感じで考えていたんですが、そこからはっきりと企画が動き始めましたね。
――さらにオリジナル脚本で連続ドラマも制作するというのはどのように決まったのでしょうか?
まず僕としてはこの企画を進めていく上で、武田さんに"船頭"でいてほしかったんですね。出会いはTBSとの共同制作の『MOZU』の劇場版だったんですが、今回はWOWOWさんに幹事会社を務めてもらいたいなと。とはいえ、なかなか規模の大きな話ですから、WOWOWの社内を動かすのもかなり大変なこと。武田さんがドラマと映画の両方という形でやるのであれば、社内を動かせるかもしれないと言ってました。そこから具体的に社内をどう動かし、企画を通したのかはわかりませんが、おそらくドラマの側には「映画をやるから」と言って、映画の側には「ドラマをやるから」と言って通したんじゃないかなと...(笑)。
ドラマのストーリーに関してはちょうど、シリーズ最新作の『ウォーターゲーム』が新聞(北海道新聞、東京新聞、中日新聞、西日本新聞)で連載されていたので、これをドラマにしようかと思ったんですが、吉田修一さんから「映画がヒットしたあかつきにはぜひ『ウォーターゲーム』を映画第2弾としてやってほしい」というお話がありまして(笑)、それならオリジナルで何か話を作ってみようということになって、いまの形になりました。
――監督自身は原作小説を読んで、どのような魅力を感じましたか? 2冊の原作を1本の映画にするということに関して"勝算"はあったのでしょうか?
この2冊の原作は、全く別のテイストのストーリーであり、それがいいんですよね。『太陽は動かない』のほうは派手なアクションのあるハードボイルド小説で、『森は知っている』は青春小説のようなテイストで、そのコントラストがすごくいいなと。この2冊をまとめて1本の物語にすることで、『太陽は動かない』の産業スパイというハードボイルドなアクションだけではない、一風変わった映画にできるんじゃないかなと思いましたね。
「原作・吉田修一」のつもりで練り上げたオリジナルドラマ脚本
――脚本は林民夫さんが参加されていますが、どのように作られていったのでしょうか?
映画のほうは原作があるので、まず『太陽は動かない』の中にどういう形で『森は知っている』のエピソードを入れていくかというところから考えて、何稿か重ねるうちにいい感じに仕上がってきました。とはいえ、実際に撮影が全て終わって、編集の段階でもどうするか試行錯誤しながらようやく完成にたどり着いたのですが。
ドラマのほうは、『太陽は動かない』よりももう少し政治色の強い物語にしていくという意向で練り上げていったのと、映画では描かれていない若き日の鷹野――南蘭島にいた17歳の頃と現在のちょうど間の時期のエピソードを作ることによって、映画を見ていなくても、なんとなく鷹野一彦という存在がわかるようにできたらという思いで作っていきました。
――吉田修一さんが監修で入られていますが、どのようなお話を?

吉田修一氏 写真:江森康之
こちら側としては「原作・吉田修一」というつもりで物語を作っていきました。映像チームの創作性を尊重するという吉田さんご自身の意向を反映し、ドラマ版のクレジットは「監修」となっていますが、基本的にはこちらから上がってくる原稿を楽しみにしてくださり、送るたびに毎回、すぐに熱いメールが返ってくるという連続でした。映画の脚本も含めて「すごく面白かった」というお話をいただけました。
――「原作・吉田修一」のつもりでとおっしゃっていましたが、ドラマ版の脚本を練る上で、シリーズらしさ、吉田修一らしさという点で意識した部分はどういったところですか?
やはり、鷹野のキャラクターというのは、すごく丁寧に原作でも描かれているんですが、感情を表に出さないタイプなので、そのあたりは踏襲して作っていきましたね。

――鷹野のバディであり、後輩エージェントでもある田岡(竹内涼真)の存在も重要ですが、彼のキャラクターに関してはどのように作り上げていったのでしょうか?
僕自身が原作を読んで、田岡は、鷹野がどうにも見捨てることができない"弟"のような存在である印象を受けました。原作のエピソードで、スタジアムのゴミ捨て場に放置されている田岡を鷹野が助けに行くくだりがあるんです。読みながら正直「そこまでして助けるか?」と思わせる描写なんですが、後々、鷹野の過去が明らかになっていくにつれて、理解できるようなところもありまして、映画での田岡のキャラクターは、原作とは違うところもあるんですが、鷹野にとっての田岡という部分は大事にしたいなと思っていました。

――またドラマの方では、若い鷹野にエージェントとしての手ほどきをする先輩・桜井(安藤政信)が登場します。オリジナルキャラクターである桜井はどのように誕生したのでしょうか?
とんでもない先輩っているじゃないですか(笑)? 僕も大学時代にそういう存在の人が周りにいたんですが、そのイメージですね。大学時代、その先輩の部屋に泊めてもらったら、いきなり「おい、ちょっとこれ磨け」ってラジカセを差し出されて、それから手書きの質屋までの地図を渡されて「そこに行って、それ売ってこい」って(笑)。質屋なんてそれまで行ったことなかったんですが「5千円になりました」って帰ってきたら「よし、飲みに行くぞ」とか(笑)。そんな感じの先輩のイメージですね。

関係性という意味では、鷹野が田岡に接するのとは正反対の感じに見せたかったんですよね。だいたい、先輩と後輩の関係って"隔世遺伝"で、1コ上の先輩のマネはしないもんなんですよ(笑)。だから桜井は、鷹野の首を絞めたりするなど、フィジカルな感じで結構、触ってくるんです。でも鷹野は田岡に対しては、絶対にそんなことはせず、わりとドライでポンっとものを投げたりする。言っていることは同じであったとしても、接し方は全然違うというのは意識しましたね。


爆破事件に列車アクション...ブルガリアだから実現した大規模ロケ
――劇場版とドラマ版はどのようなスケジュールで進行していったのでしょうか?
劇場版をひと通り、準備稿として作り終えて、それからドラマ版の脚本にとりかかるという流れでした。その後、映画のほうは、海外でのロケハンなどをして場所が決まっていく中で固まっていく部分もあって、そこで大きく脚本を直すことはありましたが、映画を撮影する段階で既にドラマ版も含めて脚本は全て出来上がっていました。
――最初から映画とドラマがセットになった企画で、両方の脚本をじっくりと作り上げた上で、撮影に入っていくという進め方はいかがでしたか?
長い1本の映画を作っているような気持ちでしたね。先に脚本をきっちりと作ってしまえば、それに合わせてロケハンをして、映画とドラマの撮影を同時に進めていくこともできるんです。これは昔とは機材が変わったという部分が大きくて、フィルムの時代だったらできないやり方でした。いまはデジタルなので映画もドラマも同じ機材で撮ることができるんです。

――WOWOWとTBSの共同制作だった『MOZU』でも、ドラマ版(※TBS版とWOWOW版)があり、その後、劇場版が制作されましたが、その時との違いはありましたか?
『MOZU』の場合は、ドラマ版が完全に終わってから映画の企画が始まったんですね。ドラマ版はTBSが10本、WOWOWが5本でしたが、後半戦の脚本が間に合わず、撮影をしながら脚本を作っていくので大変でしたね(笑)。あの『MOZU』の長さに比べると、映画1本とドラマ6本って長さとしては短いので、そういう意味では楽でしたね。

WOWOW×TBS共同制作ドラマ 「MOZU」
――日本全国、さらにはブルガリアでも大規模なロケが行われましたがいかがでしたか?
いろんな画変わりができて面白かったですね。映画とドラマを同時にやるからこそ、どちらも底上げできる部分があったと思います。ドラマの冒頭の爆破シーンは都内の設定ですが、ブルガリアで撮っています。『MOZU』も銀座の設定で爆破事件から始まるんですが、少なくとも『MOZU』は超えておきたいなという思いはありました(笑)。あれはブルガリアじゃなきゃ撮れない画だったなと思います。

ブルガリアは一度、破綻している旧共産圏の国ということもあって、すごく画がいいんです。風光明媚なロケーションで撮影するのとはまた違って、例えば共産時代の古いさびれた団地が廃墟にならずに実際にいまもそのまま使われていたりして、そのあたりの雰囲気は画として素晴らしかったですね。廃墟だとわりとどこも同じような画になりがちですが、それとはまた違うんですよね。
ロケハンが始まって、実際にブルガリアの様子を見たことで脚本がかなり変わりました。小田部教授(勝野洋/新型エネルギーの鍵を握る研究をしている大学教授)は原作では京都の大学の教授という設定、全て日本で起こる事件という設定だったんですが、そのあたりのことが、オセロが一気にひっくり返るみたいに、全部ブルガリアに変えて作ることができました。


――他にこの作品ならではの挑戦的なシーンがあれば教えてください。
(飛行機や電車、バイクなど)乗り物をたくさん使うということは意識しましたね。これは鷹野が小さい頃から「いつか"壁"の向こうに行きたい」という思いを抱えていたというのがあったので、「こいつ、やりたかったことをまさに今できてるじゃん!」というのをちゃんと見せたかったんですね。だから常に乗り物で移動しているというのはちゃんと見せたいなと。
そういう意味では"全部盛り"ができたかなと思いますね。『MOZU』などでやってきたことをベースに、それをスケールアップしたことをやりたかったんですが、それこそブルガリアでの電車でのアクションシーンで使用している車両は、実際にヨーロッパを走っている、普通は撮影では貸してもらえないようないい列車だったんです。加えて『海猿』シリーズでやってきたような大きな船でのアクションシーンなども入れることができましたし、ある意味、集大成といった感じで、いろんなものを盛り込むことができたと思います。

『ダブルフェイス』が教えてくれた「映像化不可能」を可能にする術
――主演を務めた藤原竜也さんのキャスティング、実際に仕事をされてみての印象を教えてください。
藤原さんと仕事するのは初めてだったんですが、プロフェッショナルなイメージがあって、一度やってみたいという思いは前々から持っていました。今回、ガッチリと組むことができて嬉しかったですね。このキャスティングは、もともとホリプロで長年、藤原さんのマネージャーをやっていて、プロデューサーに転身した大瀧さん(「いま、この時代にやるべき作品」を追求したい―WOWOW FILMS『泣き虫しょったんの奇跡』プロデューサーインタビュー」)がWOWOWにいらっしゃるということでできた部分が大きかったと思います。
実際にご一緒してみると、すごくタフな俳優さんですね。僕は好んで、褒め言葉としてこの言葉を使うんですがすごく"バカ"ですね(笑)。役者としても人間としても、のめり込んでいくバカだと思います!

――日本の実写映画で"産業スパイ"が主人公という設定は、どうしても現実離れしていて、どこか嘘くささを感じてしまいそうですが、藤原さんが演じていると不思議と自然に受け入れられる説得力がありました。
そうなんですよね。すごく不思議な魅力を持った役者さんで、レンタルビデオが出始めた時代のモーガン・フリーマンのような感じというか「この人がやっているならそう思えるし、面白そう」と思わせる雰囲気があるなと思いますね。なんでなんでしょうねぇ(笑)。

――田岡役の竹内涼真さんの印象についてもお聞かせください。
竹内くんも一緒に仕事をするのは初めてだったんですが、すごく気合いが入っていて、本当に体当たりで挑んでくれましたね。ものすごく撮りがいのある役者さんでした。今回、スタントマンを全然使っていなくて、その旨は事前に本人にも伝えていて、身体を鍛えてもらったりしていたのですが、そうしたハードなシーンを文字通り体当たりでこなしてくれて、素晴らしかったですね。

――藤原さん、竹内さんに対して現場ではかなりハードな要求を...?
思い返すとそうだったのかもしれないですね(笑)。その時はあまりそうは思っていなかったんですが、あとから考えるとよくやったなと思うシーンばかりです。藤原さんも竹内くんも身体能力がすごく高いので、こちらが撮る分には全く問題なかったです(笑)。本人たちは相当大変だったと思いますが...。

――これまで数々の「映像化不可能」と言われた原作を映画化されてきていますが、今回の原作も刊行された当初から「映像化不可能」と言われてきました。改めて最も難しかった部分、苦労された部分はどういったところでしたか?
正直、映像化に関してあんまり難しさを感じることはなかったんですよね。それは以前、WOWOWとTBSの共同制作で『ダブルフェイス』という映画『インファナル・アフェア』の日本版リメイクを作ったことが、すごく勉強になっています。その時の経験が以降の作品で活きているんだと思います。
『インファナル・アフェア』をリメイクする際に、脚本を再構築していったんですが、実は大元を細かく見ていくと、物語上おかしい部分、破綻している部分もあるんです。それを「エイヤ!」と力技でやってしまっているのですが、完成した映画を見た時に僕自身、あまり気にならなかったんですよね。
脚本を作っている時にどうしてもつまずいてしまう部分って出てくるんですが、香港の映画ってそこで多少、無理やりでも面白い方に振り切っていて、完成した映画ではそれできちんと成立しているんです。そこに気づけたという意味で、すごく勉強になりました。
今回の作品でも、そうやって力技で"ジャンプ"させる部分は出てくるんですが、「やっちゃえ!」という感じでやっています。だから映像化という点で今回、そこまで苦労した部分はなかったんですよね。
――今回の作品でも出てくる大規模な爆破シーンや激しいアクションは羽住作品の代名詞ともなっています。こうしたシーンを撮る上で大事にしていることは?
一番大切にしているのは、右脳(感覚)と左脳(論理)の使い分け――どうやってシャットダウンさせるか? ということですね。クライマックスシーンは、観客の左脳をシャットダウンさせないとダメなんです。そこで複雑なセリフがあったりすると、どうしても左脳が働いてしまうので、そこに関しては画の力や音楽、SE(音響効果)で見てもらわないといけない。さっきの"ジャンプ"もまさにそうなんですが、多少、辻褄が合わないこともそうすることで強引に成立したりするんです。そこは脚本を作っている段階から意識していますね。
僕が派手なシーンが好きなわけでは決してなくて...いや、好きですね(笑)。好きなんですが、そうしたシーンがあることでポーンと気持ちよく次のシーンに行けるようにしたいなと思っています。
媚びないWOWOW 「好きなものをちゃんと好きと言っていい」文化がある
――WOWOWとは『ダブルフェイス』、『MOZU』、『MOZUスピンオフ 大杉探偵事務所』に続いて4度目のタッグとなりますが、一緒に仕事をするまでのWOWOWの印象は?

(上)WOWOW×TBS共同制作ドラマ 「MOZU」/(左)「ダブルフェイス」(潜入捜査編/偽装警察編)/(右)「MOZUスピンオフ 大杉探偵事務所」
局として、特に初期の頃はメジャーエンターテインメントのど真ん中ではないイメージは持っていましたね。剛速球をど真ん中にズバッと投げ込むというよりは、変化球で勝負するような。そのイメージはいまではだいぶ変わりましたが、ただ、それでも媚び過ぎない感じがWOWOWならではという気がしますね。例えば映画版の国籍不明の女性スパイ役にハン・ヒョジュを持ってくるというのもそうですよね。普通はそこは「国籍不明なら女優は日本人で」ってなりますから。

ハン・ヒョジュ
――実際にWOWOWのスタッフと一緒に仕事をされてみての印象は?
初めてWOWOWさんと一緒に仕事をしたときは正直、どこに向けて球を投げればいいのかわかっていない部分があったんです。というのは、映画であれば興行収入という結果があり、民放のドラマであれば視聴率があり、そこに勝ち負けがあるんですね。そういう意味で、WOWOWさんの場合、加入されている方が見るので、そこでどういう結果が出るかはあんまり意味がないんじゃないか、と思っていました。
もちろん、それは間違った考えで、いまの時代、何が見られているかもハッキリとわかるし、視聴率よりもシビアな形で誰がどこまで見て、どこで視聴をやめてしまったかまで把握できるんですよね。そういう勘違いが解消されたことで、あまり「WOWOWならでは」ということを難しく考えることはなくなりました。
一緒に仕事をさせていただいて、「映画が好き」、「エンターテインメントが好き」といった「好き」というものを持っている人が多いなと思います。地上波のドラマ制作で出会う人たちと比べて、WOWOWのみなさんからは、普段の何気ない会話や打ち合わせでの発言の端々から、そういった「好き」というのを感じるというか、「好きなものをちゃんと好きと言っていいんだ」という空気を感じられて心地いいですね。

――WOWOWだからこそ実現できることというのはありますか?
それこそ今回の『太陽は動かない』みたいなことをできるということですかね。これは地上波だったらなかなかできないし、できたとしてもテイストやアプローチはかなり変わっていただろうと思います。
――最初に企画を進める段階で羽住監督からWOWOWに対して「今回は地上波キー局は(出資社として)入れないで、"WOWOW"として作品を背負ってほしい」とおっしゃったそうですね?
自分の中ではまだ、メジャーエンターテインメントの大作で「WOWOWの映画!」という印象がガツンと残っていなかったので、今回は製作委員会の3番目、4番目にWOWOWの名前があるんじゃなくて、一番上にWOWOWの名前があるようにしてほしいと伝えました。先ほども話しましたが、武田プロデューサーに先頭に立って作品を引っ張ってほしいという思いが強かったんですね。
――昨今、配信系のサービスの台頭もありますが、監督自身はその影響をどのように感じていますか? また、クリエイターの目線でWOWOWの今後に対して、提言やアドバイスがあればお願いします。
僕自身、配信系サービスに関してはまだ様子見の部分もあるんですが、やはりいろんな部分がガラリと変わっていくでしょうね。ただ、劇場に足を運ぶ人々が減るのでなければ、映画作品を見る機会が増えるというのはいいことなんじゃないかなと思っています。配信系サービスももっと日本で映画を作ってくれたらいいなと思います。
そのなかでWOWOWさんに関しては、これまでもずっとたくさんの作品を作ってきていますからね。このまま質を落とさずに多くの作品を作り続けるということが大事だと思います。
「好き」という思いこそ最強! 多くの人に見てもらうために考えるべきこと
――改めていまの時代に映像作品が持つ力、魅力というのはどういう部分にあると思いますか?
映像ということで言うと、『トムとジェリー』は本当にすごいなと思うんですよね。子どもを連れてちょっとカフェに入ったら、たまたま小さなスクリーンで流れていたりして、音が聴こえなくてもずっと釘付けになって見ているんです。『ミニオンズ』なんかもそうですよね。そういう光景を見ると、ずっと影響力を持ち続けている映像のすごさを感じますね。

――ハリウッドとの比較という点で、今後の日本映画界がどうなっていくと思いますか?
登場するキャラクターの多様性という点に関して、ハリウッドは徹底していて、すごいですよね。世界中でヒットするだけのことはあるなと思うし、日本はそのあたりに関しては遅れているし、そもそもそういう作りをしなくてもいい、日本国内の市場だけで成立してしまっている映画業界だったので、これから大変かなと思いますね。でも、日本にはいい漫画もたくさんあるので、コンテンツ的にはすごく豊かだと思います。。
――監督が今後、実現させてみたいこと、やってみたい企画などはありますか?
アトラクションムービーみたいなものを作り続けていきたいですね。先ほどのヒットの法則じゃないですが、若い人たちが仲間を誘ってこぞって映画館に足を運んでくれるような「あのワクワクドキドキをもう一度感じたいし、仲間にも共有してもらいたいから来る」という作品――ディズニーランドのアトラクションに何度も乗るように楽しめる2時間の映画を作りたいですね。
――最後にWOWOWのM-25の旗印である「偏愛」にちなんで、お仕事をされる上での監督の偏愛、大切にされていることを教えてください。
好きなことをみんなが楽しんでやるということが、いいものを作る上で大切なことなのかなと思いますね。エンターテインメントは作っている側が楽しめないと、見ている人たちを楽しませることなんてできないと思います。
やはり「好き」というのが一番強いんです。その人が好きなものを、好きなように作れるチームというのが、いい作品を作れる組なのかなと思います。みんなの趣味性が全開になっている。でも、それが決して自己満足ではなく、大勢の人が見て楽しめる方向性で発揮されているようにすることが大事ですよね。

――監督ご自身は自分が作りたいものと、ヒットさせるために作らなくてはいけないものの間で葛藤を感じることはないんでしょうか?
それはあまりないですね。こっちの方がいいと思っていたが、そうじゃなかったといった気づきは常にあるんですが。僕の場合、編集の途中で一度、"野面(のづら)プレビュー"というのをやるんです。通常プレビューというものはプロデューサーと監督と編集マンで何度か編集した作品を見直すものであり、毎回まっさらな気持ちで作品を見ようと思うものの、やはり自分たちで作業しているので、なかなかそれが難しくて、単なるチェックになってしまいがちなんです。
そこで僕が初見の感覚でプレビューを見るために、原作さえも読んだ事がなく、その作品にスタッフィングされていない業界関係者たちと一緒に見るんです。その人たちと映写室で一緒に作品を見ていると「あ、ここはちょっと早すぎるな」とか「意味がわかりづらいな」ということが、不思議とわかってくるんです。もちろん、終了後に感想を聞いたり、アンケートを取ったりもするんですが、それ以前に初見の人たちと一緒にその空間で作品を見るだけで純粋に見えてくるものがあるんです。
僕は、そこで得る感覚というのを大事にしているので、普段からあまり「やりたいこと」と「やらなくてはいけないこと」の間で葛藤するというのはないんですよね。この仕事を「やりたいことをする仕事」だとも思っていないというか...。そもそも、自分が本当にやりたいことと劇場用映画の間に大きなギャップがあるなら、この仕事自体を選ばずに、例えばYouTuberになればよくて。昔と違っていくらでも機材もあって、低予算で劇場映画と変わらないクオリティで作ることも可能なので。
僕の場合、自分がやりたいことと劇場映画における制約との間に、基本的にズレはないので苦になりません。「大勢に見てもらう」ということが大事なので、そのために「このキャストが必要」ということであれば、それでいいと思うし、そこで「本当は...」とモヤモヤを抱えながらやるということは全然ないんです。


『連続ドラマW 太陽は動かない -THE ECLIPSE-』(全6話)
2020年5月24日(日)より放送開始 毎週日曜午後10:00~
■WOWOWドラマ版公式サイトはこちら
■映画版「太陽は動かない」公式サイトはこちら
インタビュー/黒豆直樹 撮影/祭貴義道