第1回 WOWOWクリエイターアワード表彰式&松永大司監督インタビュー

「第1回クリエイターアワード」表彰式開催! 最優秀賞「2020年 五月の恋」松永大司監督が語る、アワード創設の意義とWOWOWの果たす役割の大きさ
WOWOWが、自社で制作したオリジナルコンテンツを対象に、チャレンジ精神あふれる企画への取り組み、卓越した企画の成立に貢献した優秀なクリエイター、プロデューサー、ディレクター、技術者個人を表彰する「クリエイターアワード」を創設。その第1回の表彰式が6月1日に開催され、最優秀賞に輝いたドラマ「2020年 五月の恋」の松永大司監督をはじめ、優秀賞を受賞したドラマ「殺意の道程(みちのり)」 脚本・主演のバカリズムさん、「連続ドラマW コールドケース3 ~真実の扉~」の撮影監督を務めた山田康介さん、「松尾スズキと30分の女優」 脚本・演出・出演の松尾スズキさん代理の大人計画・長坂まき子社長らが出席した。表彰式後には、最優秀賞の松永監督にインタビューを敢行! リモートでのドラマ撮影、WOWOWとのドラマ制作について振り返ってもらった。
日本では珍しい、スタッフ・クリエイターを表彰するアワード
5月14日に発表されたWOWOWの長期ビジョン「10年戦略」「10年戦略ステートメント」に基づき、クリエイターとの協業を促進させるべく新設されたこちらのアワード。通常、アワードというと俳優や監督を表彰するものがほとんどだが、同アワードではコンテンツプロデューサー、ディレクター、テクニカルディレクター、IT・CGクリエイターなどを対象としていることが大きな特徴といえる。
<優秀賞>「殺意の道程」脚本・主演:バカリズム
最初に壇上に立ったのは、優秀賞「殺意の道程」の脚本・主演を務めたバカリズムさん。表彰状には「社会派ドラマの多い当社のオリジナルコンテンツにおいてサスペンスコメディという新たなジャンルに挑んだ」「主人公2人が復讐を進める上でいろいろな人と出会い、生きる喜びに気付いていく人間ドラマの側面は、コロナ禍にあり、塞ぎがちな世の中に笑いと喜びを与えた」「日常にある小さな違和感の積み重ねがもたらす笑いの数々は、バカリズム氏が持つ観察力と脚本力があってこそ」など、作品の魅力、それを作り上げたバカリズムさんの功績をたたえる言葉が綴られた。
 バカリズムさんは「いままでやったことのないジャンルだったので、すごく新鮮な気持ちで楽しくやらせていただきました。いつもなら、打ち合わせや脚本を出した段階で「もっとこうしてほしい」とか言われることがあるんですが、(同作は)全く言われず(笑)、毎回「いいですねぇ。やりましょう!」という感じで自由にやらせていただいて、しかもこんな賞までいただきまして、本当にありがとうございました」と受賞の喜びを口にした。
バカリズムさんは「いままでやったことのないジャンルだったので、すごく新鮮な気持ちで楽しくやらせていただきました。いつもなら、打ち合わせや脚本を出した段階で「もっとこうしてほしい」とか言われることがあるんですが、(同作は)全く言われず(笑)、毎回「いいですねぇ。やりましょう!」という感じで自由にやらせていただいて、しかもこんな賞までいただきまして、本当にありがとうございました」と受賞の喜びを口にした。

<優秀賞>「連続ドラマW コールドケース3 ~真実の扉~」撮影監督:山田康介
続いて、同じく優秀賞に輝いた「連続ドラマW コールドケース3 ~真実の扉~」の撮影監督の山田康介さんが壇上へ。「出演者をして『俳優と一緒にお芝居する』と言わしめたキャメラマン」「世界初のリメイクとして取り組んだ本シリーズが、国内はもとより本国からも絶賛されたことは当社の誇り」と山田さんが本シリーズで果たした功績をたたえた。
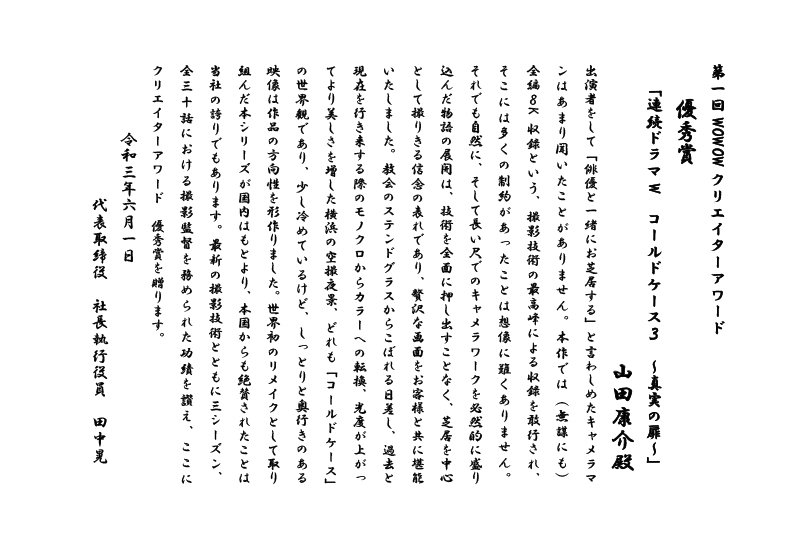 山田さんは、WOWOWで自身が撮影した作品が10作品を超えたことを明かし「毎作品、思うのはクリエイティブに対する理解が深くて、僕も結構、クレイジーなことを言っちゃうんですけど(笑)、他の会社であれば『その機材はダメ』と言われることも多いのに、WOWOWさんはなんとかして実現させようと工面してくださって、本当に助かりました。『コールドケース3~』を撮っている間、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言でストップしてしまったんですが、その間も補償してくださったり、そういうことがクリエイターにとっては励みになります」と現場のクリエイターをサポートするWOWOWの体制に対し、感謝を口にした。
山田さんは、WOWOWで自身が撮影した作品が10作品を超えたことを明かし「毎作品、思うのはクリエイティブに対する理解が深くて、僕も結構、クレイジーなことを言っちゃうんですけど(笑)、他の会社であれば『その機材はダメ』と言われることも多いのに、WOWOWさんはなんとかして実現させようと工面してくださって、本当に助かりました。『コールドケース3~』を撮っている間、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言でストップしてしまったんですが、その間も補償してくださったり、そういうことがクリエイターにとっては励みになります」と現場のクリエイターをサポートするWOWOWの体制に対し、感謝を口にした。

<優秀賞>「松尾スズキと30分の女優」脚本・演出・出演:松尾スズキ
優秀賞受賞者の3人目は「松尾スズキと30分の女優」の脚本・演出・出演を務めた松尾スズキさん。この日の表彰式は欠席となったが、代わりに「大人計画」の長坂まき子社長が出席した。
表彰状では「4人の女優とともにゾンビや蕎麦屋、殿となり、荒唐無稽な世界観を構築。その唐突な設定こそが共演者の個性を引き出し、演技の振り幅に魅了されました」「コロナ禍において塞ぎがちな状況に、大いなる笑いを届けてくださいました」と称賛の言葉が贈られた。
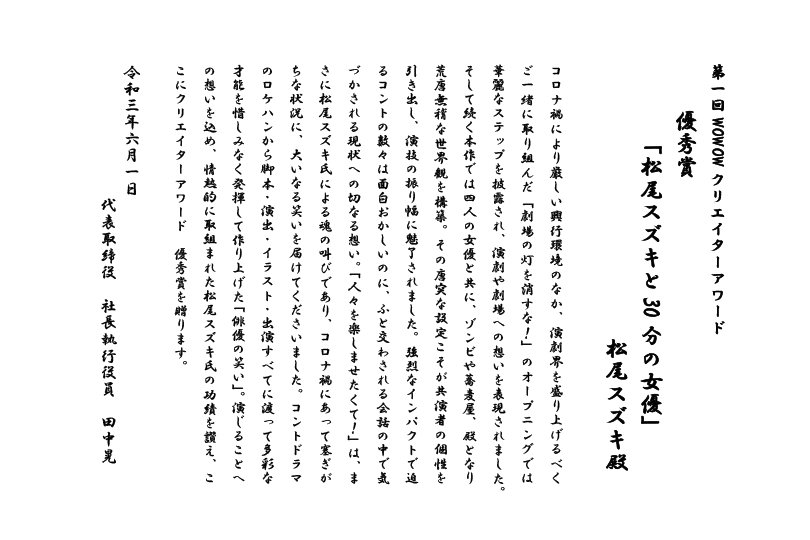 長坂社長は松尾さんの手紙を代読。「偏った作品を作らせていただき、それを評価していただける。出演者、スタッフの理解と頑張りがあってのことだと思います。これからも妥協せず、わが道を行かせていただきます」という言葉に大きな拍手が湧き起こった。
長坂社長は松尾さんの手紙を代読。「偏った作品を作らせていただき、それを評価していただける。出演者、スタッフの理解と頑張りがあってのことだと思います。これからも妥協せず、わが道を行かせていただきます」という言葉に大きな拍手が湧き起こった。

「チーム力で勝ち取った賞」
<最優秀賞>「2020年 五月の恋」:松永大司監督
そして最後に最優秀賞の「2020年 五月の恋」の松永大司監督が壇上へ。
表彰状には、松永監督の受賞理由が以下のように綴られた。「コロナ禍において、従来通りの撮影が出来ず、思うように制作に取り組めない中、発想の転換をもって、俳優・監督・撮影監督が一切顔を合わせず、リモート制作に挑戦された本作。昨日までの日常が終わり、"ニューノーマル"なる言葉が語られた2020年5月、とても自然に、いままでと変わらない日常を切り取った素敵な物語が誕生しました。その背景には、幾多の試練と不自由があったことは想像に難くありません。しかし、その制約を楽しむかのように、生き生きと指示をされる松永監督の熱意が、脚本に魂を吹き込み、スタジオにおいてひとりで葛藤する役者を力強く導くことで、離れているからこそつながりを感じる奇跡を見事に演出されました。新たな技術と向き合い、短期間でまとめあげた圧倒的なリーダーシップはこのコンテンツにおけるエンジンそのものであり、類まれなる創造力と実行力に敬意を表します」
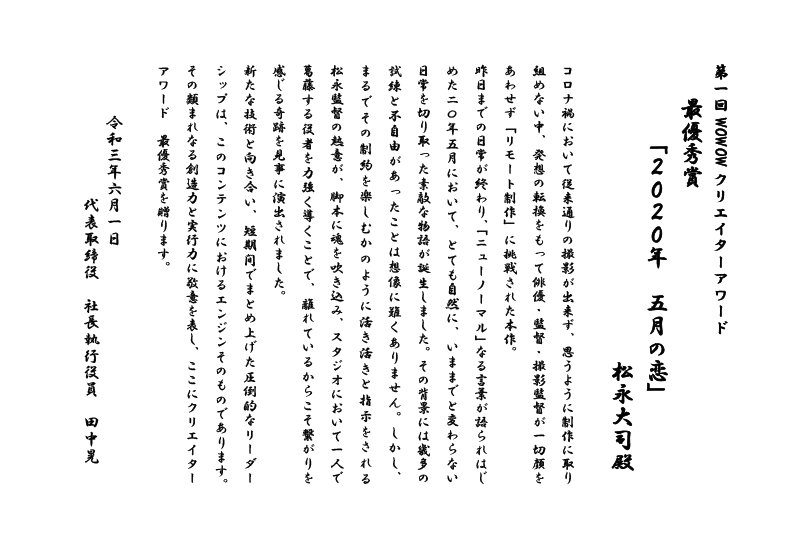 松永監督はこの受賞理由に触れ、「作品について、あたかもリモートではないかのような状況で作品を見てもらえたことを評価していただいたんですが、現場では逆に僕が『これ、リモートってことが言い訳にならないですから』と言わせていただき、それをチームが本当に体現してくれました。そういう意味で、僕がいただいた賞ですがチーム力で勝ちとった賞だと思っています」とまず何よりスタッフ、キャストを含めた制作チームへの感謝を口にする。そして「賞をいただいたことで終わりではなく、今回が第1回ということも含め、ここで最優秀賞を取った松永がWOWOWとこういう作品を作ったんだということで、僕の最大の恩返しになるのではないかと思っています。ですので、ぜひ次の企画を進めさせてください(笑)」と笑いを交えつつ、受賞の喜びを語った。
松永監督はこの受賞理由に触れ、「作品について、あたかもリモートではないかのような状況で作品を見てもらえたことを評価していただいたんですが、現場では逆に僕が『これ、リモートってことが言い訳にならないですから』と言わせていただき、それをチームが本当に体現してくれました。そういう意味で、僕がいただいた賞ですがチーム力で勝ちとった賞だと思っています」とまず何よりスタッフ、キャストを含めた制作チームへの感謝を口にする。そして「賞をいただいたことで終わりではなく、今回が第1回ということも含め、ここで最優秀賞を取った松永がWOWOWとこういう作品を作ったんだということで、僕の最大の恩返しになるのではないかと思っています。ですので、ぜひ次の企画を進めさせてください(笑)」と笑いを交えつつ、受賞の喜びを語った。

「おめでとうございます」ではなく「ありがとうございました」 クリエイターたちの作品作りへの姿勢は「WOWOWの誇り」
この表彰式で、賞状を授与する際に「おめでとうございます」ではなく、あえて「ありがとうございました」とクリエイターへの感謝の言葉を口にしていた田中社長。最優秀賞を受賞した「2020年 五月の恋」について、田中社長は「初めて見たとき、芝居のエチュード(即興による芝居)をやっているのかと思ったら、ほとんど岡田惠和さんの脚本通りと聞いてびっくりしました。それくらい緻密に計算されてできていて、そこに演技がしっかりと入っていて、舌を巻きました」と称賛の言葉を贈るとともに、あらためて全受賞者に「皆さんの作品を作る姿勢一つ一つが、WOWOWの誇り、プライドとなっていることに感謝申し上げます。ぜひともまたWOWOWで良い作品を作っていただきたいと思います」と語った。
表彰式後には松永監督にインタビューを実施し、あらためて受賞の喜び、作品に込めた想いなどを語ってもらった。
緊急事態宣言下のリモート撮影で企画から放送まで数週間......チーム力の勝利!
――まずは今回、「2020年 五月の恋」が高く評価され、第1回クリエイターアワードの最優秀賞を受賞したことについて、どのような想いでいらっしゃいますか?
どんな作品を作った時も、作品を評価していただけるのは嬉しいことではあるんですが、とくに去年のコロナ禍で、どうやったらエンターテインメントがお客様、視聴者に力を与えることができるのか?について、多くの作り手たちが悩みを抱えていたと思います。そのなかで、試行錯誤して作品を作って――授賞式でも言いましたが、チームで作った作品だなと思っているんですけど、それを評価していただけたことは、特別な想いがありますね。
――コロナ禍という、エンターテインメントにとっても受難といえるこの時期に、WOWOWがこうして「クリエイターアワード」という、作り手を表彰する賞を創設したことについては、クリエイター側からどのような意義を感じていらっしゃいますか?
"監督"という立場においては、賞をいただくようなアワードは、映画祭などを含めて世の中にいくつもあるんですが、撮影監督であったり脚本家であったり、"クリエイター"という大きな枠組みの中では、なかなかスポットライトを当ててもらうことって難しいと思うんです。
普通に作品を見ている視聴者も、クレジットに名前が載っていたとしても、どういう人が作品を撮っているのかをそこまで気にするわけではないので。それでもやはりスタッフあっての結果ですので、そこにスポットライトを当てていただけるのは、スタッフのモチベーションにも大きく関わってくると思います。
それは本当に大切なことで、この国にはそういう賞がなかなかないんですよね。もっと増えるべきだとも思いますね。
――先ほどの表彰式で、受賞者に贈られる賞状には、それぞれの受賞の理由、評価されたポイントが綴られていました。
そうなんですよね。いわゆる賞状の"定型文"ではなくて、ちゃんとこの作品をどう評価したかってことをあれだけ長い文章で書いてくださっていて、あぁ、本当にこの作品を評価してもらえたんだなと嬉しかったです。
 ――あらためて「2020年 五月の恋」の制作について、お聞きします。昨年の緊急事態宣言下で制作された本作ですが、そもそもの作品の企画・発案は主演を務めた吉田羊さんだったそうですね。あの時期にこういう企画の監督のオファーが届いて、どのように受け止められましたか?
――あらためて「2020年 五月の恋」の制作について、お聞きします。昨年の緊急事態宣言下で制作された本作ですが、そもそもの作品の企画・発案は主演を務めた吉田羊さんだったそうですね。あの時期にこういう企画の監督のオファーが届いて、どのように受け止められましたか?
最初に話をいただいたのが4月末か5月初旬で、それから撮影・放送まで数週間で行なったんですが、僕はこれまで、自分自身で「こういう企画をやりたい」と考えて、プロデューサーとその企画を形にしていくことが多かったんですね。それが今回は、吉田さんが発案し、岡野(真紀子)プロデューサーと話をして、脚本家の岡田惠和さんも乗っていて、もうひとりの主演の大泉洋さんもやる気満々という状態で、僕はいちばん最後に船に乗るという状況だったので、コロナ禍は別にして、こういう形で企画に乗ることを楽しんでみようという気持ちがありました。
その中で、すべてリモートで撮影するのは挑戦だなと思ったので、チームを信じて何ができるかをディスカッションしながら進もうと。まずは皆さんと顔を合わせて、いろんなことを決めていこうって思っていました。
――実際、辰巳スタジオ内のWOWOW Labに監督がいて、吉田さん、大泉さんもそれぞれ別の場所にいるという完全リモートでの撮影はいかがでしたか?
僕の監督としてのスタイルは、カメラマン次第ですごく変わるんですね。というのは、現場でやることはほとんど変わらず、演出し、リハーサルをした上で「じゃあ、どう撮るかは(カメラマンに)お任せします」という流れなんです。今回はiPhoneを使っての撮影で、映画『花束みたいな恋をした』などで撮影監督をしている鎌苅洋一が参加して、カメラのアングルを作ってくれました。
なのである程度、演出をして、リモートでリハーサルを数日やって、鎌苅も芝居を見た上で「アングルは任せるよ」というスタイルでした。逆に言うと舞台などと一緒で、本番が始まったらこちらは手を出すことはできない状態で、1カットで撮っていたので「失敗しないでくれ!」と思いながら見ていましたね。なので「あぁ、舞台の演出家ってこういう感じなのか......」という感覚はありましたが、演出に関しては、それ以前にいつも通り厳しく(笑)、吉田さんにも大泉さんにもかなり細かくやらせていただきましたので、その意味で、撮影の技術的な面に関してはリモートだからというもどかしさなどはなかったですね。
第1話を丸ごと撮り直しのトラブルも吉田羊さんとの信頼関係があったからこそできた!
――吉田さんとは映画『ハナレイ・ベイ』に続いてのお仕事ですね。同作の時もかなり厳しく演出されたそうですが、そういう意味では今回も変わらず、リモートではありつつもかなり厳しい要求を?
そうですね。1カット15分ほどなんですけど、1話目の本番を撮影して、吉田さんとしても大泉さんとしても納得のテイクを撮ることができたんですが、尺の関係で「明日、またもう一度撮ります」ということになってしまったんですね。その時は2人とも「なんでまたやるんですか......?」となってしまいまして......(苦笑)。
それぞれ離れたスタジオにいらっしゃるので、1対1で電話でお話させていただいたんですが、吉田さんには納得いただいて、続いて大泉さんとお話をしたときは「いや、僕はいいんですけどね、羊ちゃんがねぇ......。大丈夫かなぁ......? 監督、何が不満なの?」と言われましたね(苦笑)。
ただ芝居の問題ではなく長さの問題で、1カットで編集ができないので、もうちょっとテンポをアップしてということだったんです。吉田さんとは「ハナレイ・ベイ」をやっていたからこその信頼関係があって「松永さんがそう言うならやります」と言っていただけたので、そこは本当に感謝しかないですね。
――直接、顔を合わせて話ができないというところでの難しさはありませんでしたか?
それはありましたね。それこそ大泉さんとは今回が初めてで「初めまして」も「お疲れさまでした」もすべて画面越しで、ドラマアワードの際に初めて同じ空間で「初めまして」とごあいさつをさせていただいたんです。
演出って自分の言葉のトーンや空気感も含めて通じたりするので、画面を通して2次元の映像で話をしてもなかなか伝わらないことはあって、むしろ電話のほうがよくて、電話に切り替えて話をさせてもらったこともありました。そういう意味で、顔が見えているからいいというものでもなかったりするんですよね。そこは難しかったですね。演出の距離感に関しては、そこにいないとなかなか難しいなと。
部屋にたったひとり......リモート撮影が俳優に及ぼす思わぬ効果とは?
――逆にリモートであることが、作品にとってプラスになった部分はありましたか?
それは吉田さんも言っていたんですが、部屋にまったく誰もいない状態なんですね。スタジオを借りて、カメラをセッティングしたら、その場には俳優以外、誰もいないんですよ。通常ならカメラマン、録音スタッフなどがいるんですけど。
そういうやり方は、役者にとって「自意識を外す」という意味で良いやり方なのかもしれないなと思いますね。「カメラの前で演技している」という意識が外されていくんですね。小さなiPhoneがあるだけで、あとはひとり暮らしのリビングそのものなので。そうやってひとりになれたということは大きかったと吉田さんも言っていましたね。
――先ほど今回の企画に関して「最後に船に乗った」とおっしゃっていましたが、こういう形で参加されてみていかがでしたか?
自分で企画をゼロから立ち上げると、良くも悪くもなんですが、がんじがらめになってしまう部分はあると思います。でも、こうやって後から船に乗ると、決して監督としての頑固さを放棄するわけではないんですが、どういう経緯、想いでこの企画が立ち上がり、進められてきたのかを考えようとするので、ジャッジするレンジが広くなる――良い意味で無責任になれるところがあるなと感じています。
「あぁ、僕はこう思うけど、そういうやり方でやるのなら、それを決定、遂行していきましょう」と後ろに付いていく瞬間があって、それは面白いですね。
――監督のこれまでの作品は、むしろ監督自身の経験や内側から湧き上がってくる想いを形にしたような、作家性の強さが大きな特徴であり、魅力だったと思いますが、それとは異なるスタイル、スタンスでの参加が良い経験になったということですね?
そうですね。それこそ映画『トイレのピエタ』であれば、窓の清掃の描写一つを取っても、僕自身が窓ふきをやっていた経験があるからこそ「窓ふきってこうなんだよ!」って感じだし、人物像も僕のバイト先にいた人たちを参考にしているから、バイト先の人たちがあの作品を見たら「これはあの人だな」とすぐ分かるくらい、僕の経験が描かれています。その熱量が作品に反映されていると言えますが、逆に言うと、どうしてもレンジは狭くなってしまいますよね。
あと、やはり、ひとりでやれることって限界がありますから、何でも自分の経験と想いだけで物を作れるかというと、それは違う。これから先、10年、20年の僕の監督としてのキャリアを考えたとき、自分以外の誰かの強い想いの込められた企画に乗せてもらって、そこに共感しつつ、自分なりの料理の仕方をしていくということをしない限り、作品を作り続けていくことはできないだろうなと思います。
――そういう意味で、今回、WOWOWと仕事をされてみて、いかがでしたか?
すごくやりやすかったですね。それは決してこちらが言うことに対してすべて「YES」ということではなく、プロデューサーの意見もありつつ、最終的にこの作品がどうあるべきか? ということを撮影のギリギリまでディスカッションをしている感じでした。岡野プロデューサーもそうですし、技術面をサポートしてくださった篠田成彦さん("芯を食った異端"の精神で時代の半歩先を進め! WOWOW Lab 映像担当が語る、眼福を提供するWOWOWクオリティ)もそうですね。
誰もやったことのないリモートの撮影ということで、どこかで制約もありつつ、柔軟に思考していかないといけない局面があるんですね。最終的には、プロデューサーがリスクを負えるか? というところが大きいんですが、そこで信頼してリスクを背負っていただけました。作り手を尊重していただけたなと思いますし、本当にやりやすい現場でした。
 ――脚本に関しても、松永監督は普段ご自身で書かれることが多いですが、今回は岡田惠和さんの手による脚本を演出されてみていかがでしたか?
――脚本に関しても、松永監督は普段ご自身で書かれることが多いですが、今回は岡田惠和さんの手による脚本を演出されてみていかがでしたか?
(岡田さんの脚本が)本当に素晴らしかったですね。ラストに関して少し提案させていただいたり、途中のニュアンスを少し変えさせていただいたりはしたんですが、それらの提案にも納得してくださって、僕が勝手に思っているだけかもしれませんが(笑)、とにかく相性の良い脚本家さんだなと感じています! 今回、岡田さんとお会いできたのはすごく大きな経験になりました。またぜひご一緒させていただきたいと思います。
「決定権を持つ人間が多くなれば純度は下がる」――みんなの顔が見える規模のチームで大きな作品を撮ることの重要性
――WOWOWについて、これまでどのような印象を持たれていましたか? また今回、仕事をされて、その印象は変わりましたか?
やはり作品自体オリジナリティーがあって、良い意味でとがった作品をやっているなと思っていました。うまく形容する言葉がないんですが「ブランドがあるな」と。
今日の授賞式に参加してみて、自分たちでモノを作っているという自負を持っているんだなと感じましたし、みんなの顔が見える規模の組織で作品を作っていて、もちろん、通る企画もあれば通らない企画もあるとは思いますが、WOWOWのスタッフの血の通った作品を作っているんだなと。それはすごく魅力的なことだと思います。
作品の規模がどんどん大きくなっていけば、関わる人の数も多くなっていくのは当然で、そういうなかで僕も作品を作っていかないといけないとは思っています。でも、作品の純度の高さで言えば、多くの人の意見が入れば入るほど、どうしても純度は薄まってしまいます。そういう意味で、あぁWOWOWってこういうスタンスでモノ作りをしていて、この雰囲気が反映されているんだなというのを今日あらためて感じました。
決定権を持つ人が少ない中で大きなものを作ったほうが絶対に面白いものができると思っているんですけど、邦画でよくある製作委員会方式で作っていき、みんなの意見を立てていったら、そりゃ純度は薄まりますよね。こうやってWOWOWのようなスタンスで作品を作れるならば、他とは違うものができる可能性、高いポテンシャルがあるんだというのを感じました。
ひと言で形容はできないんですよね。例えば「NIKEってどんなブランドですか?」と聞かれたら「NIKEってNIKEだよね?」としか言えないというか......。僕からすると、それと同じで「WOWOWってWOWOWです」としか言えないんです。
――表彰式でも「次の企画を」とおっしゃっていましたが、今後、WOWOWで作ってみたい作品、やってみたいことなどがあれば教えてください。
映画を自分の仕事の軸としてやっているなかで、連続ドラマというのはあまりやってこなかったので、今回は1話15分でしたが、短い作品を連続で撮っていくというのがすごく面白かったんですよね。そういう意味で今回、連続ドラマをやってみたいということを思わせてもらいましたね。もちろん内容も大事ですが、表現の形態として連続ドラマってすごく面白いなと。
――具体的に映画と連続ドラマの違いをどのような部分に感じていらっしゃいますか?
難しいですが、まずメディアが違うというのは大きいですね。映画の大きなスクリーンで上映するのか? 小さな画面で見るのか? 出口の違いがありますよね。
あと、何話もエピソードを積み重ねられるというのも大きいですね。2時間でまとめないといけない映画に対して、60分のドラマを10話となると全部で600分ですからね。表現の幅が広がりますね。僕自身、海外ドラマも好きでよく見ているので、やりたいという気持ちはありますね。
――ぜひ松永監督による「連続ドラマW」を観たいです。
それはもう、こちらとしてもぜひ! 「松永に撮らせてください」と書いていただければ(笑)。僕もどんどん、企画を出させていただきます。
今回のクリエイターアワードの意義について、リリースされた文章を読ませていただいて、「WOWOWはクリエイターをサポートする側の集団であり、監督や脚本家、カメラマンを抱えているわけではないからこそ、クリエイターへの恩返しの想いを込めて」という内容だったんですけど、僕ら監督もひとりでは作品を作ることはできないんですね。そこにはプラットフォームが必要で、予算があり、プロデューサー、制作スタッフがいて、初めて仕事が成立するんです。
どんなに監督が「やりたい」と言っても、それを成立させるためにたくさんの人がいないとできない。今回こうして受賞させていただいて、それが次の作品へとつながっていくなら、本当に意味のあることだなと思っています。

取材・文/黒豆直樹 撮影/祭貴義道




